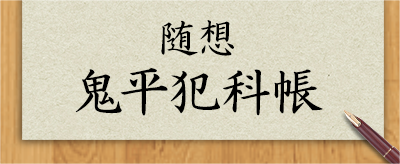新鬼平随想録
第12回『おれの弟』
109話の「おれの弟」(『オール読物』昭和53年10月号。文春文庫18巻)は、平蔵と小柳安五郎が極めて危険な仕事をする物語である。
梅雨が上がって猛暑となり、外に出ないでいると妻・久栄に注意されたので、平蔵は翌朝御家人の隠居の姿をして、市中見廻りに出かけた。
しかしすぐ平蔵は
男は本所・高杉道場の平蔵の弟弟子、滝口丈助である。丈助は貧乏御家人の次男ゆえ一心不乱に剣の修業をし、今や小石川の一刀流・高崎道場で代稽古をするまでになったが、依然剣一筋で、平蔵が勧めても妻帯しない。そんな丈助だから、女の方がここへ誘ったのであろうと平蔵は思った。
一方、女は小日向の表具師・今井宗仙の後妻、お市であった。平蔵は昨年宗仙宅で会ったが、年は33歳前後、品があり、言葉使いも正しく、若い頃武家奉公していたと見た。2人の取り合わせが意外なので、女中に調べさせると、2人は初めての客で、女客は殆んど食べず、勘定を払ったという。
駕籠に乗ったお市を見送った丈助が徒歩で去って行くと、平蔵は弟同様に可愛がってきた丈助が人妻と色恋をするのはよくないと思い、尾行を始めた。すると音羽の刀剣師に入り、研いだ大刀の包みを抱いて現われ、小石川の心行寺にある住居へ向った。
胸さわぎがした平蔵は、密偵の五郎蔵・おまさ夫婦が住む駒込に急ぎ、おまさには役宅へ行き、小柳同心を連れてくること、五郎蔵には丈助の見張りを頼んだ。小柳が到着すると、平蔵は2人で心行寺近くの友人の旗本屋敷へ行き、長屋の一間を借り、そこから小柳と五郎蔵が交替で、丈助の見張りに出かけることにした。
午前3時頃小柳が長屋へ来て、丈助が起きたというので、平蔵が心行寺へ来ると、丈助は井戸の水を浴び、腹ごしらえをし、間もなく出発する様子と五郎蔵に告げられる。そして提灯を持って現れた丈助は、緊迫した、ただならぬ気配である。
空が白みはじめる頃、丈助は高田の南蔵院に着き、裏の松林中の野原で決闘の準備をするので、木陰から平蔵が出ようとした瞬間、1条の矢が飛んできて丈助の胸元に突き立った。3人が走り出ると、彼方の松林からも5人の侍が走り出て、その内の1人が大刀を振りかざし、矢が立ったまま大刀を構えた丈助を襲い、その大刀を叩き落す。これを助ける間もなく3人は応戦し、1人倒した平蔵が「盗賊改め方長谷川平蔵。弓矢を使い、5人で襲うとは卑怯。名乗れ、何者だ」と
丈助が住居に残した平蔵宛の書状を読むと、7千石の旗本・石川筑後守(ちくごのかみ)の三男・源三郎は家臣を連れ高崎道場に入門しているが、真剣の勝負を申し込んできたので、道場の高弟・森田某を立合人にして、承知をしたとある。とすれば立合人は来なかったし、6人の侍は源三郎をはじめ石川家の者ということになるので、平蔵は丈助の手紙をたずさえ、若年寄・
また平蔵は、お市に秘かに別れをさせてやろうと手配したが、夫と共に現われ、「この度は兄が」といって泣くので、驚いた。聞くとお市は丈助の亡父がさる座敷女中に生ませた妹で、昨日兄が橘屋で5日後に決闘するというので、何としても止めようと思っていたという。平蔵も(この泰平の世に、決闘のどこがいいのだ)と心の中でいい、初めて泪ぐんだ。
さらに高崎道場を調べた結果、当主は丈助を養子にして跡を継がせる決意であったが、源三郎が反対し、真剣勝負を申し入れ、だまし打ちにしたことが分かった。平蔵は備前守に報告し、御公儀による御裁きをお願いしたが、秋になって備前守に呼び出され、「かの一件は忘れてもらいたい」と言い渡された。石川筑後守は将軍の
翌年の晩春のある朝、空が白みはじめる頃、石川源三郎と家来1人は日課であるが、馬で広尾ヶ原に現われた。源三郎が馬を飛ばした後振り返ると、家来ははるか後方なので笑って馬を歩ませる。その時、首に投げ縄が巻きついた家来が木陰へ引きずり込まれ、覆面の男の
源三郎がまた振り返ると、馬しかいないので、馬首をめぐらそうとした時、前方から騎乗の侍が来る。気にせず家来の方へ走り出すと、侍が横に並び、棍棒で胸をつき、源三郎は落馬するが、すぐ大刀を抜き「何者だ。石川源三郎と知ってか」と叫ぶ。
「いかにも」といって下馬した侍は平蔵である。「弟の
源三郎は大刀を振りかぶり、平蔵の頭上に打ち込み、平蔵も源三郎に躍り込み、両者が入れ替った時、平蔵の
人影一つない広尾ヶ原の木立の中から覆面の男が馬で現われた。
「小柳。よく助けてくれたな」
「私も胸がはれましてございます」
「御役にある者のなすべきことではなかったかも知れぬ。なれど堪こらえ切れなんだわ。さ、戻ろう。畜生ばたらきの盗賊を1人斬ったのと同じことよ」
「そのとおりでございます」


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる