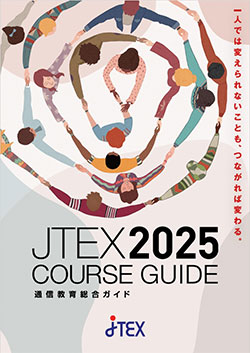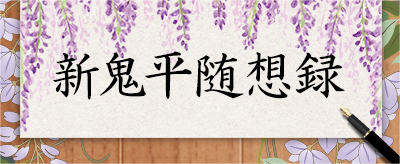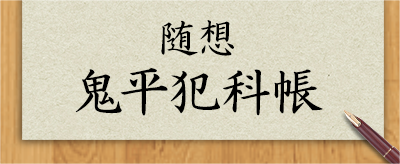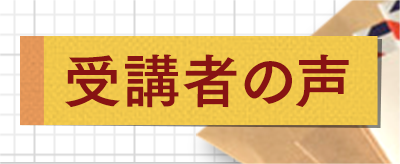メールマガジン
2025年夏期に試験が実施される人気資格に関して紹介します! /連載:ものづくり人のためのドラッカー[その13]
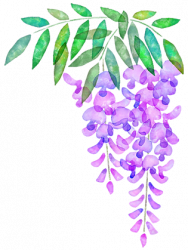
*2025年5月8日(木)
皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日は、
- 2025年夏に試験が実施される人気資格
- 新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」その13
について、ご案内いたします。ぜひ最後までご拝読いただければ幸いです。
夏は資格試験の季節です!
年初に「今年こそは資格取得にチャレンジするぞ!」と心に決めたまま、春を迎えてしまった方も多いと思いますが、まだ間に合います!
本記事を読んで、自分に合った資格を見つけてみてください。
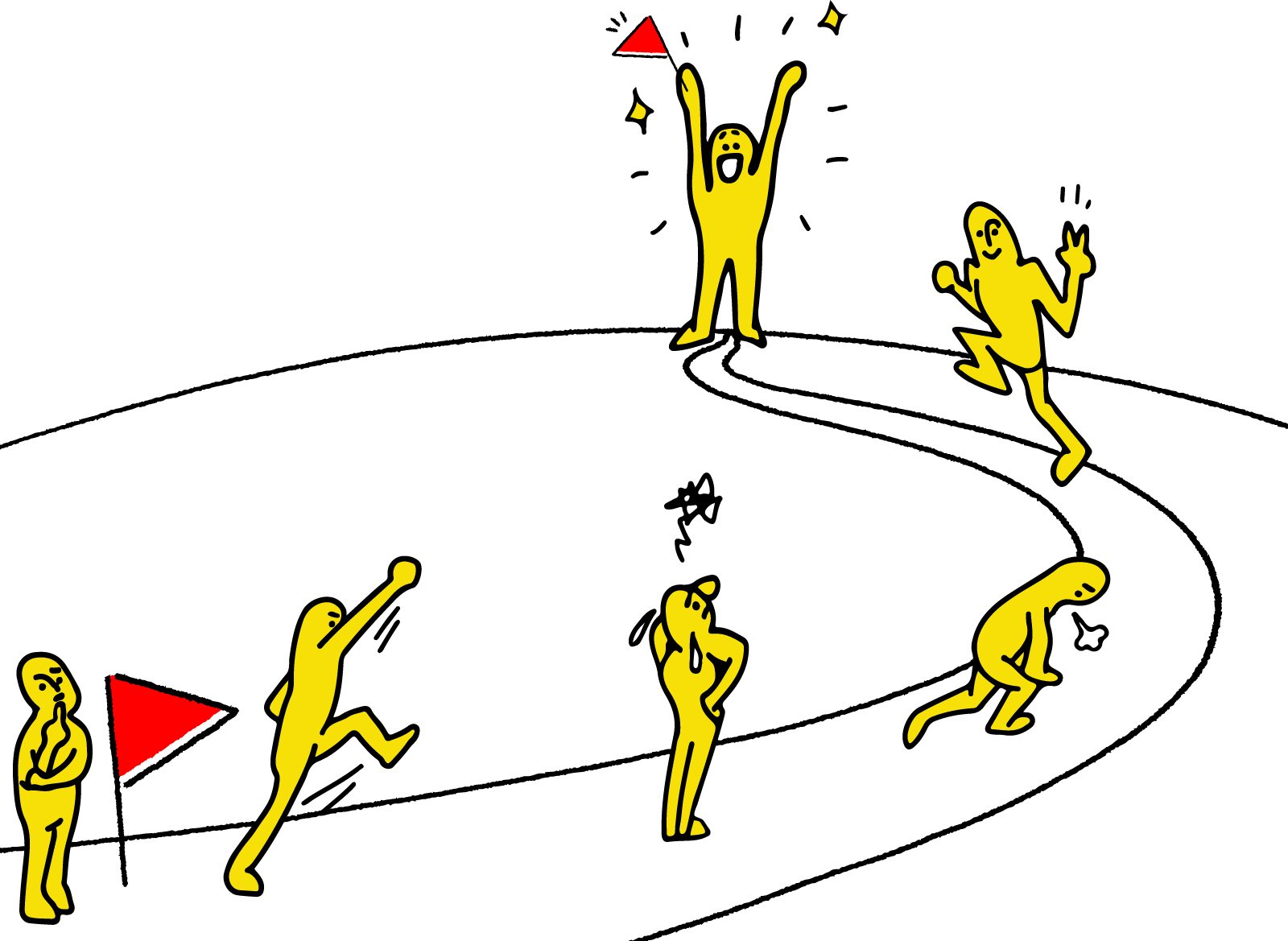
6月から9月に試験実施される資格例
QC検定(品質管理検定)

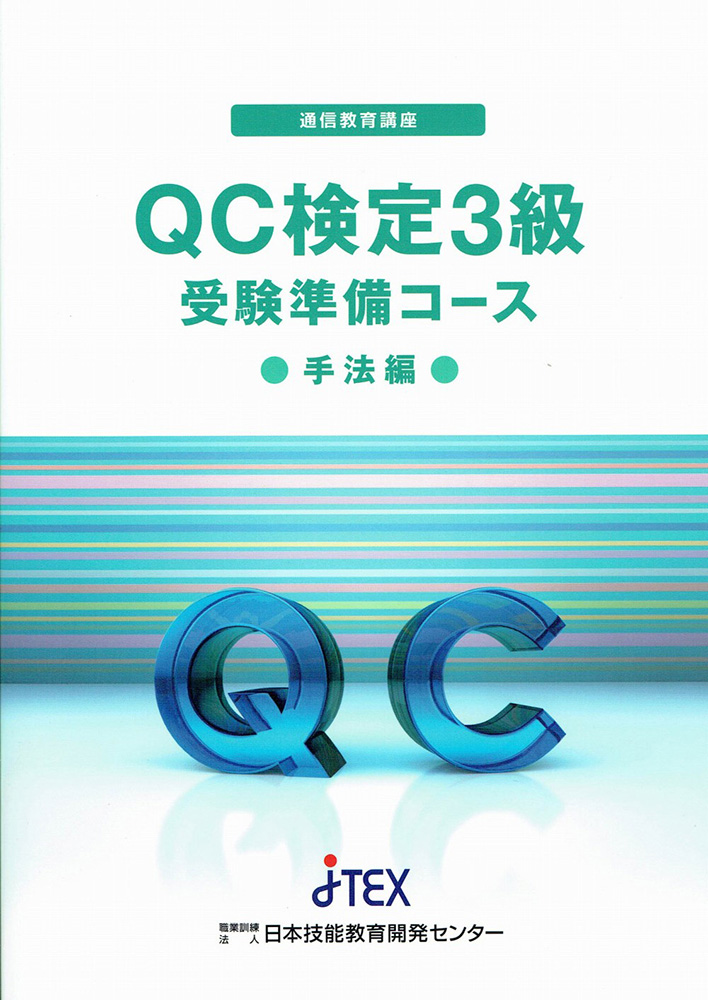
QC検定®は「品質管理検定」とも呼ばれ、品質管理に対する知識がどれくらいあるのかを客観的に評価できる資格です。資格取得のための勉強は、品質管理に携わる社会人だけでなく、高校生や大学生にとっても役立つ知識を得られると評価されています。
下記ではメーカーで勤務する方には必須の知識であるQC検定に関しての情報を紹介していきます。
エネルギー管理士
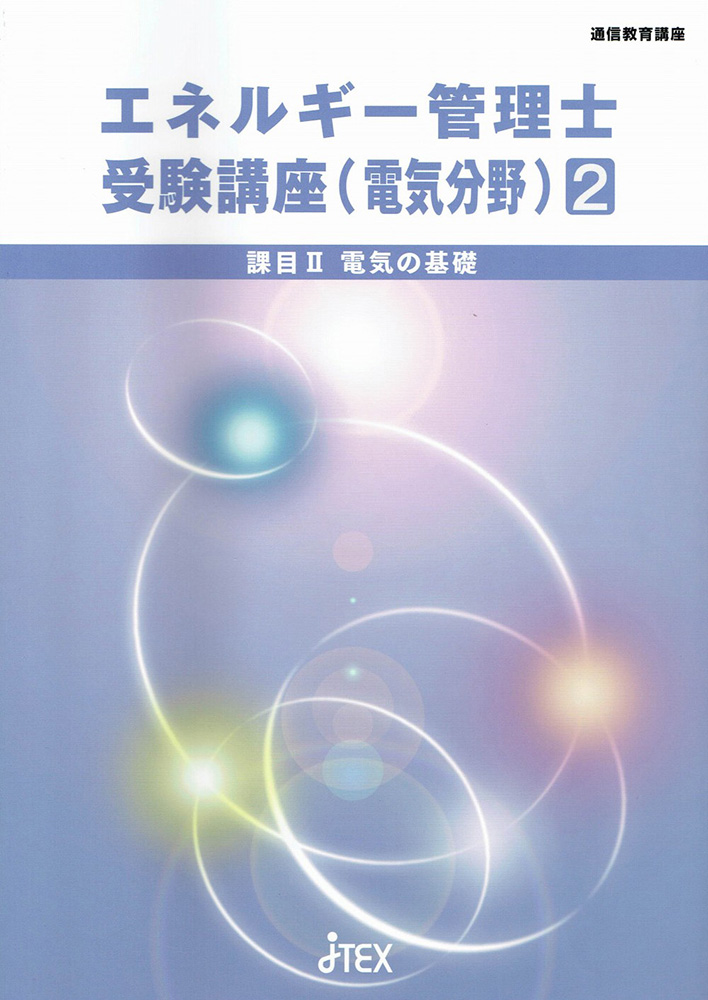
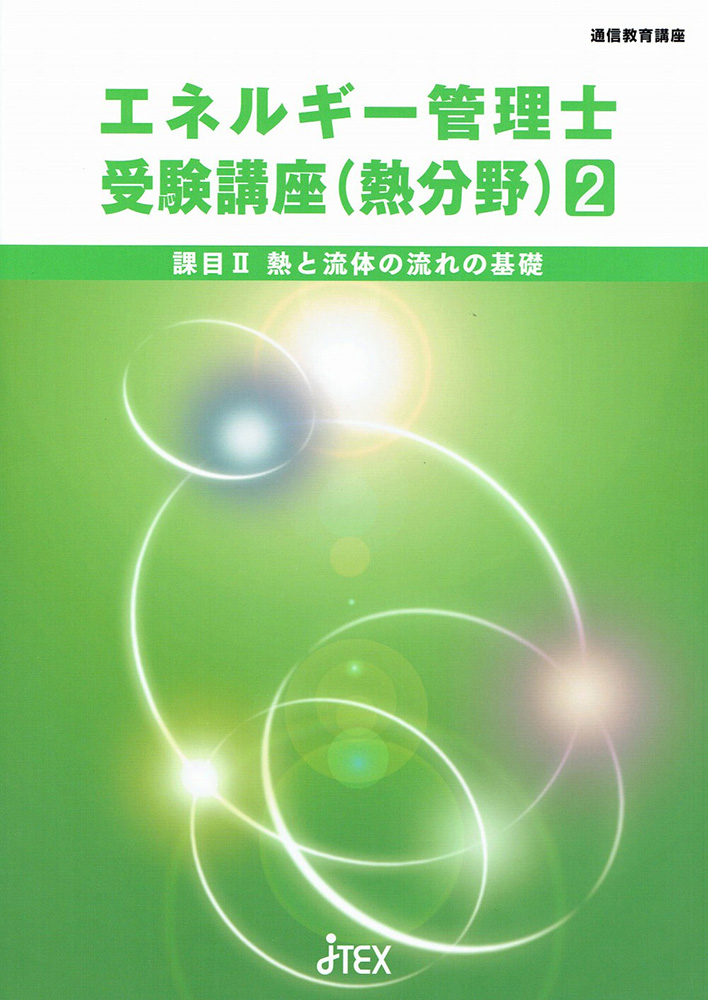
エネルギー管理士は、2006年に省エネ法により定められた国家資格で、工場内のエネルギー使用方法の改善、管理をするための国家資格です。規定量以上のエネルギーを使う工場には、本資格を所持する者がいなければいけないと定められています。以前は熱管理士、電気管理士と別個の資格でしたが、現在はエネルギー管理士(熱分野/電気分野)としてまとめられています。
下記では、需要も高まっている専任資格であるエネルギー管理士に関しての情報を紹介していきます。
毒物劇物取扱者
※毒物劇物取扱者試験は東京では7月実施となり、各都道府県で実施時期が異なります。
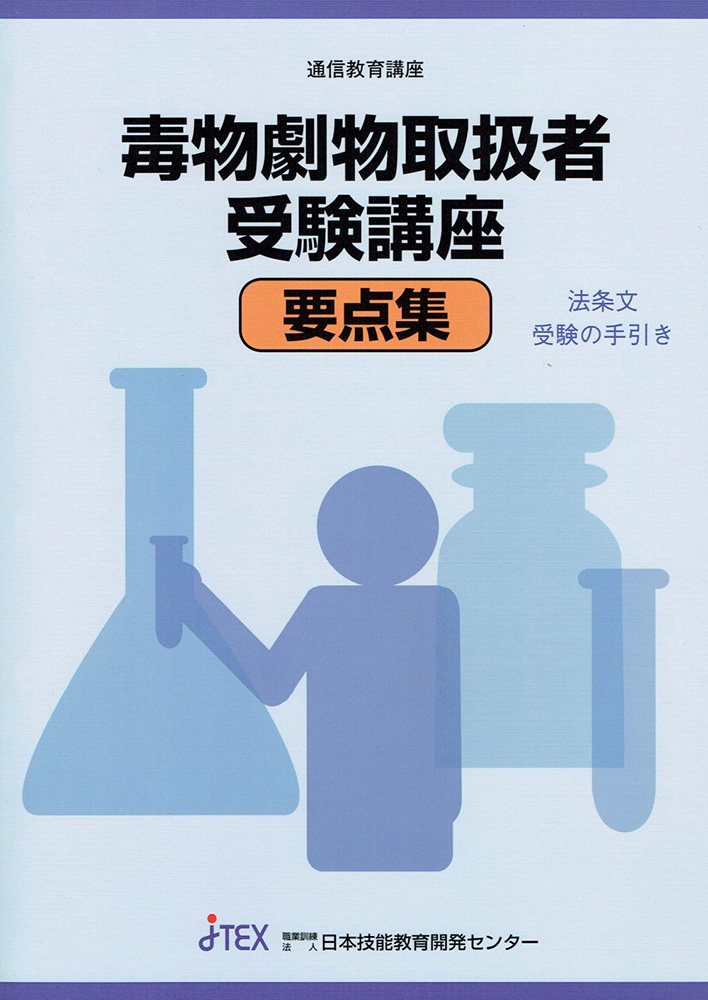
毒物劇物取扱責任者は、毒物及び劇物の輸入、製造や販売を行い、管理・監督するのに必要な国家資格で、毒物及び劇物取締法により定められています。青酸カリや硫酸等の毒性・劇性の強い、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業を行うためには、専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たることが義務付けられています。
下記では専任資格であり、社会的必要性も高い、毒物劇物取扱者を取得するメリットや、実際の業務内容、試験の詳細等を解説していきます。
ここまで夏期に試験が実施される3つの資格に関して説明してきましたが、JTEXではその他の各種国家資格等の試験対策講座もご案内が可能です!
下記、2025年通信教育総合ガイドで希望にあった資格を探してみましょう!

新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」
~イノベーションは天才のひらめきではなく、明日に向けた仕事である
著者 浅沼 宏和
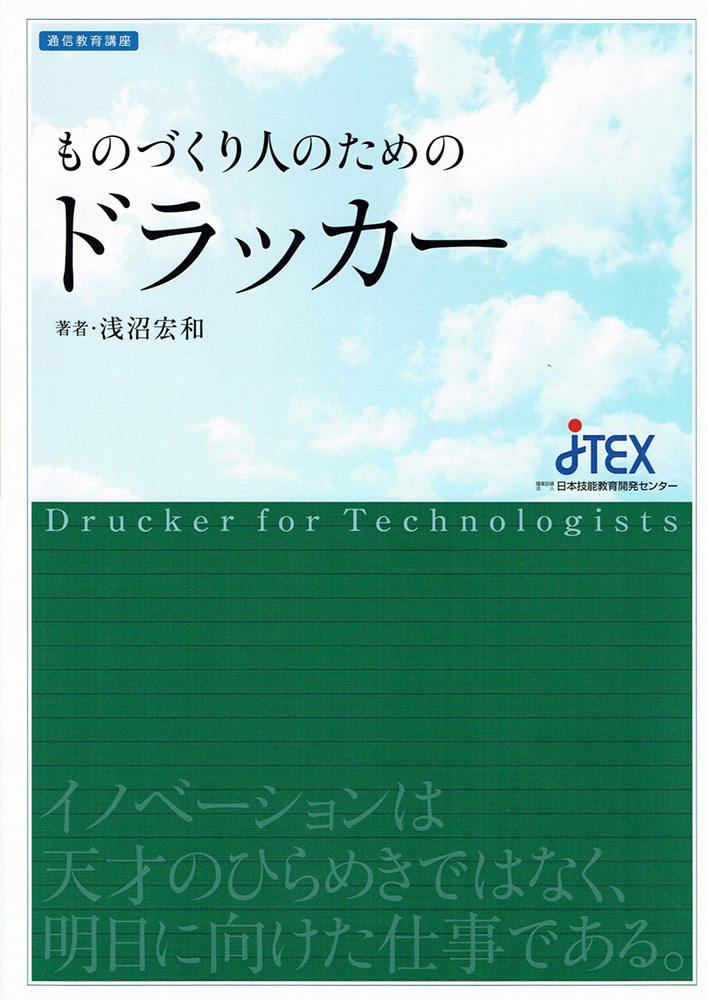
“ものづくり人“とは、ものづくりに関わる、経営者、技術者・技能者、営業・管理部門までのすべての人を、そう呼んでいます。
この連載はドラッカーの11冊の著書からリベラルアーツとしてのドラッカーをまとめたものです。
どこかに、役に立つ一言が含まれていることと思います。
ぜひ、引き続きご愛読いただきたく、連載を開始いたします。
その13 知識労働の目的と質
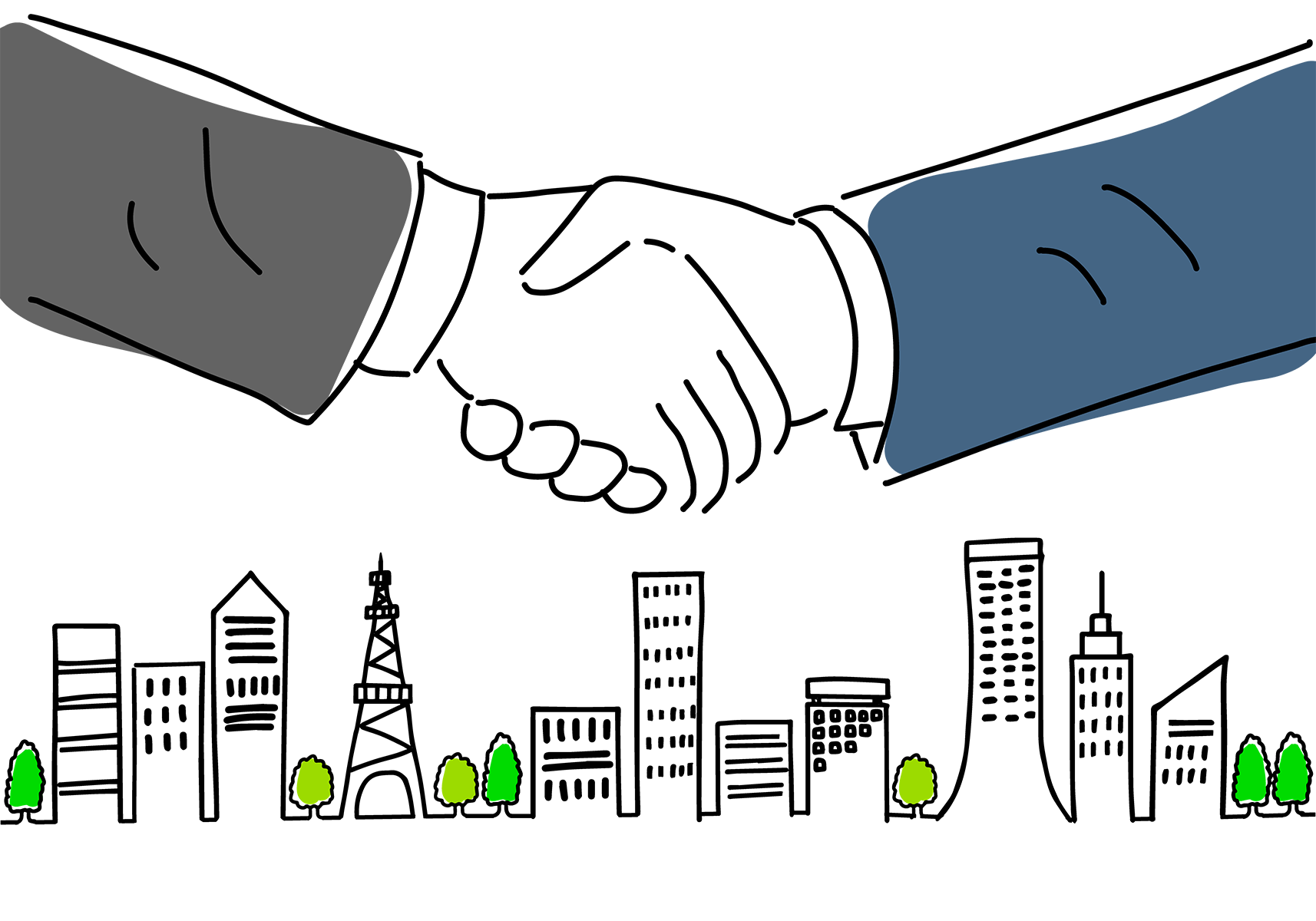
知識労働で最も重要なことは、仕事の目的を決めること。
肉体労働は仕事においてやるべきことが明確に決まっていて、それをどのような方法で行うかが重要となり、仕事がプログラム化されていると言えます。しかし、知識労働は肉体労働のように、目的が最初からはっきりしているわけではありません。
ドラッカーはこのように説明しています。
「知識労働では、仕事がプログラム化されていることはほとんどない。確かに、患者が意識不明に陥った緊急時に看護師が行うべきことは、あらかじめプログラム化されている。しかし、日常において、患者の面倒を見るか、事務処理をするかを決めるのは看護師自身である」
知識労働がプログラム化されていないために、知識労働者の多くが本来やるべき仕事に十分集中できていないのだと、ドラッカーは言うのです。成果をあげるためには、時間をまとめ、成果の上がる仕事に集中的に時間を使う必要があります。しかし、多くの知識労働者はそれが十分にできていないのです。知識労働の生産性が低い原因がここにあります。
知識労働の生産性を向上させるためには、
・知識労働者自身が自らの仕事の目的と内容を明らかにし、その仕事に集中する
・その他のことはできる限りやらないようにする
ことが大切なのです。
ドラッカーは次の例をあげています。看護師たちが自分の仕事を定義したところ、「患者の看護」と答えるグループと「医師の補助」と答えるグループに分かれました。しかし、「仕事の邪魔になるものは何か?」という問いについては「書類作成や電話応対などの雑務」と意見が一致しました。
そこで、各種雑務を事務員に任せることで看護師の生産性が二倍になったというのです。
知識労働においては仕事の「質」を検討する必要がある
知識労働において、質は「仕事の本質」であり、仕事の生産性の中心に据えるべきものです。そして、それは最低の基準ではなく、最高の基準もしくは最適の基準を念頭に置くべきものなのです。
肉体労働は量の面から取り組むべきものであり、知識労働は質の面から取り組むものなのです。知識労働では、いくつの仕事をしたかではなく、その仕事の中で本当に成果のあったものがいくつあるかが問題なのです。
知識労働の中には、手術の成功率のように仕事の質を測定できるものもありますが、ほとんどの仕事が主観的な評価がなされているにすぎず、知識労働のマネジメントは発展途上と言えます。
ドラッカーは教師の仕事は「何人の生徒が本当に理解できたか」で評価されるとすると考えていましたが、目的の定義によって、その質は大きく変わってくると説明します。かつて、米国の公立学校では、「恵まれない子が学ぶことを助ける」ことが目的となっており、この結果、教育の面での成果をあげることはできませんでした。他方、成果をあげていた私立のミッションスクールでは「学びたい子が学べるようにする」ことが目的となっていたといいます。教育レベル面での定義では、前者は失敗を基準にして定義し、後者は成功を基準にしていたために、成果に違いがあるのです。
仕事の定義は質の定義の方向性を決めるもので、とても重要なのです。
ある医薬品メーカーは、「確実性の高い既存の医薬品の改良」を重視しており、別の医薬品メーカーでは、「リスクはあるが革新的医薬品の開発」を重視しています。それぞれの仕事の目的が明確になれば、その目的にかなった研究開発の質の定義が決まります。
仕事の質とは、仕事の定義の仕方そのものに関係するものであり、何を成果にするかは、意見が分かれるものであり、どれが正解というものはありません。
仕事の質を定義することは、リスクを伴う意思決定なのです。
このため、仕事の目的や質の決定までには、真摯な姿勢で建設的な議論を積み重ねることが不可欠です。
次回 その14「資産としての知識労働者」
著者紹介
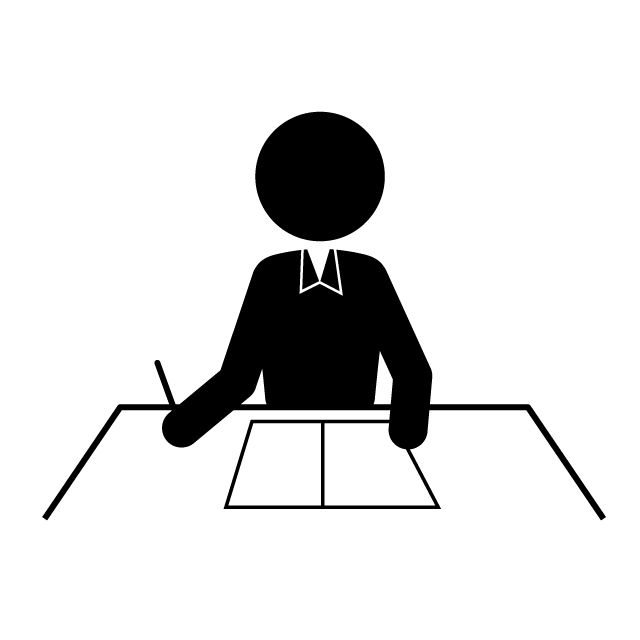 浅沼 宏和
浅沼 宏和
早稲田大学政治経済学部卒、中央大学大学院法学研究科卒、名古屋学院大学 論文博士
「社会制度変容の力学 -内部統制制度・リスクマネジメント・コーポレートガバナンス一体化の論理」
講座に関するご質問、その他通信教育に関するお問合せは、下記担当者までお願いいたします
2025年総合通信教育ガイドについて
ご請求は下記より受け付けております
「一人では変えられないことも、つながれば変わる。」


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる