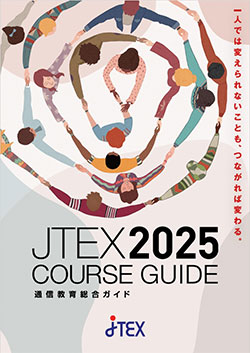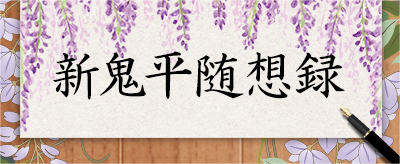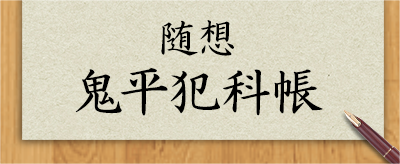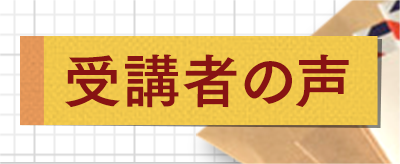メールマガジン
第40回 QC検定®(品質管理検定®)申し込み受付中です! /連載:ものづくり人のためのドラッカー[その22]

*2025年7月10日(木)
暑さ極まる頃となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
体調を崩しませんようご自愛くださいませ。
本日は、
- 第40回 QC検定®受験申込」
- 新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」その22
について、ご案内いたします。ぜひ最後までご拝読いただければ幸いです。
第40回 QC検定®(品質管理検定®)申し込み受付中です!!

1級・2級(筆記試験)
- 試験日:2025年9月28日(日)
- 申込受付期間
- 【団体申込(団体A/団体B)】
・申込受付(クレジットカード払い):2025年6月2日(月)~2025年7月18日(金)
・申込受付(コンビニ店頭現金払い):2025年6月2日(月)~2025年7月13日(日)
・団体登録期間:2025年6月2日(月)~2025年7月10日(木)
・団体登録後の申込書アップロード:2025年6月2日(月)~2025年7月18日(金)
3級・4級(CBT試験)
※第40回よりCBT試験(コンピュータ試験)となりました
-
・【試験実施期間】:2025年6月23日(月)~9月28日(日)
・申込受付期間:2025年5月8日(木)~8月24日(日)
・【受検チケット購入期間(団体)】:2025年5月8日(木)~7月18日(金)
まだお済みでない方はお早めにお申し込みください。
JTEXではQC検定®2級とQC検定®3級の受験準備講座をご用意しておりますので、ご紹介させていただきます。
2色刷りで重要ポイント・キーワードがよく分かる!!
試験では、実務ではなじみのない用語も出題されるため、事前にしっかり学んでおく必要があります。JTEXのテキストは2色刷りで、重要語句が一目で分かり、項目ごとに学習レベルの段階を分けて表しているので、効率よく勉強することができます。
試験対策だけでなく、現場に役立つ知識が身につく!!
QC七つ道具や計算問題も具体的な事例で分かりやすく解説していますので、試験対策としてだけでなく、仕事にも役立つ実践的な知識が身につく内容となっています。
実際の試験に即した練習問題、レポート問題を解くことにより、実力を養成します。
試験実施団体日本規格協会発行の過去問題集(3年分収録)も付いており、万全な体制で合格へ導きます。


統計解析ソフト付きコース
複雑で難しいQC検定®2級の手法分野の計算を、簡単に行うことができ、なおかつ実務にも活用できる統計解析ソフト(CD-ROM)が付いたコースです。
ご好評をいただいております
受講者の方々からも
-
「テキストの内容が充実しており今後の業務に役立ちます」
「基本から応用まで幅広く網羅されていました」
とご好評をいただいております。
QC検定®合格へ向けて、JTEXの通信教育講座をぜひご検討ください。
今後の試験日程
- 【第41回】
- 1級・2級(筆記試験)
- 3級・4級(CBT試験)
-
・試験日:2026年3月15日(日)
・申込受付開始:2025年12月中旬(予定)
-
・試験実施期間:2025年12月中旬~2026年3月中旬(予定)
・申込受付開始:2025年10月中旬(予定)
QC検定®合格へ向けて、JTEXの通信教育講座をぜひご検討ください。
新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」
~イノベーションは天才のひらめきではなく、明日に向けた仕事である
著者 浅沼 宏和
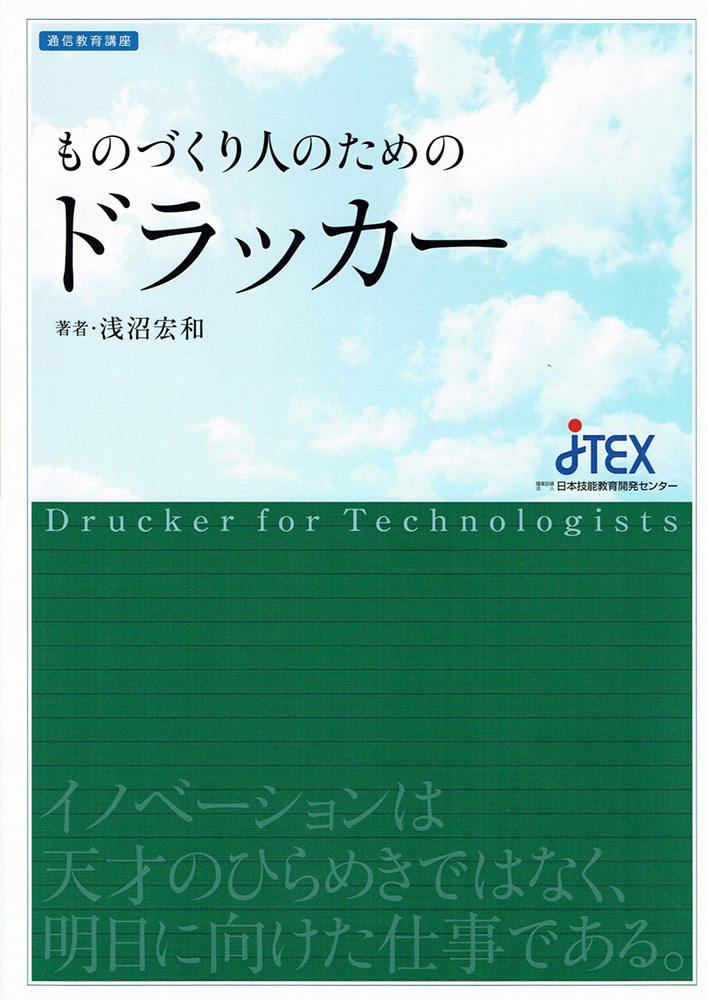
“ものづくり人“とは、ものづくりに関わる、経営者、技術者・技能者、営業・管理部門までのすべての人を、そう呼んでいます。
この連載はドラッカーの11冊の著書からリベラルアーツとしてのドラッカーをまとめたものです。
どこかに、役に立つ一言が含まれていることと思います。
ぜひ、引き続きご愛読いただきたく、連載を開始いたします。
その22 製造とテクノロジスト
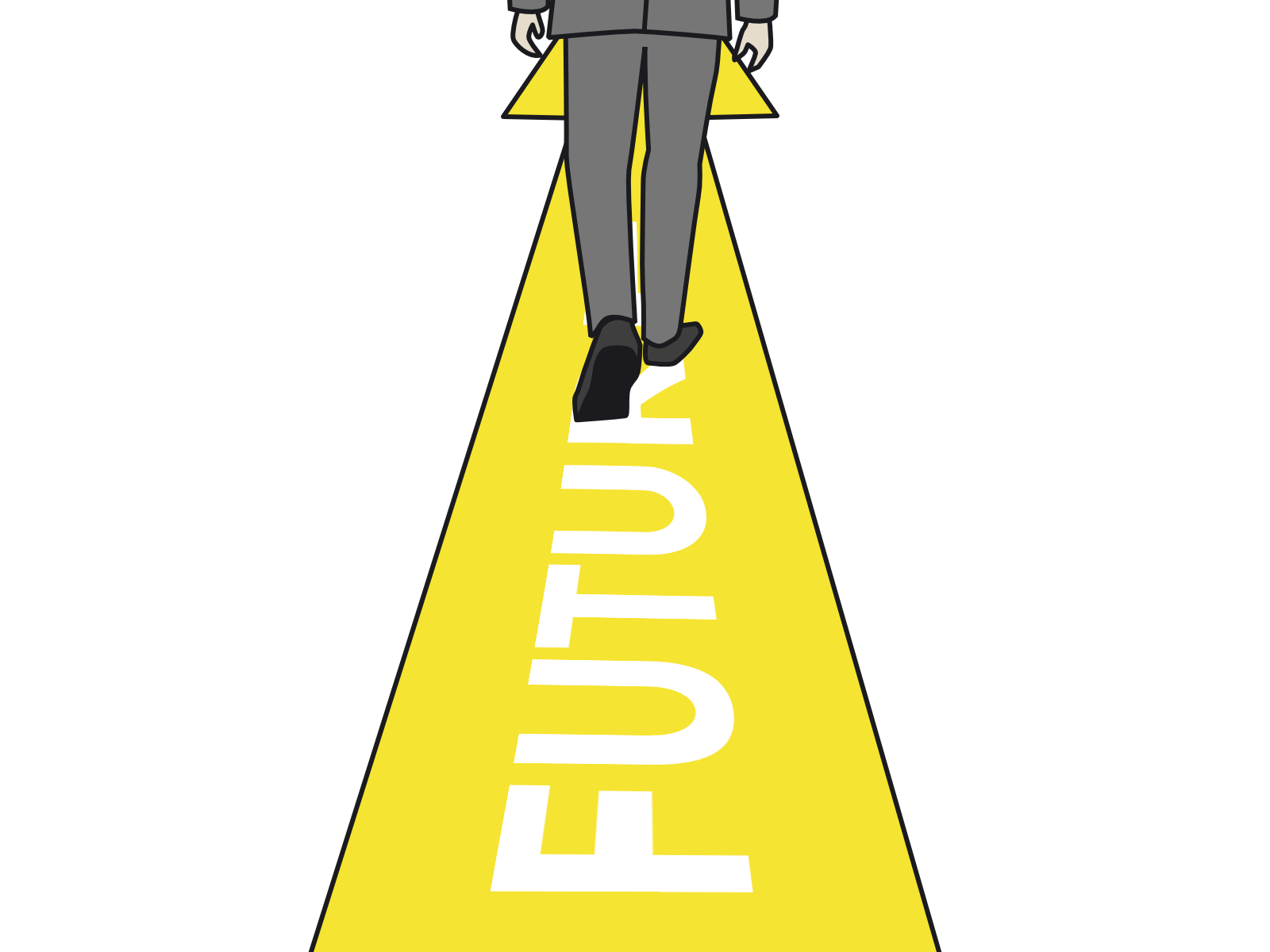
ここまで、部分の合計を超える全体としての製造という観点から、四つのコンセプトを紹介してきました。四つのコンセプトは、それぞれが工場を別の側面からとらえようとするもので、ドラッカーのポストモダンという視点に基づくものです。
「統計的品質管理」は人間が働く場所として工場をとらえていました。製品の品質と仕事のやりがいを両立させるための視点を工場にもたらしたのです。
「新しい原価計算」のコンセプトは、工場を仕事が行われる場所としてとらえ、すべてのコストを時間という観点からとらえようとするものでした。
「フレキシブル大量生産」のコンセプトも仕事自体に着目し、規格化と多様化の両立によって大きな成果をあげようとするものでした。
「システムとしての製造」のコンセプトは、すでに場所という見方すら持たないものでした。原材料に価値を加えるプロセスという意味を持つもので、最終消費者の理解を要求するものでした。
部分の合計を超える全体という視点こそ、製造に新たな展開をもたらすものとドラッカーは考えていたのです。
19世紀において、工場は作業や設備の集合体としてとらえられていました。それが、テイラーの科学的管理法によって、一つひとつの作業を検討した後に、新しい仕事に組み立て直されるようになりました。20世紀の花形であったテイラーの考え方によれば、それぞれの活動の合計が成果であると見なされました。組み立てラインや原価計算は、そのような全体に立つものでした。
しかし、新しい製造のコンセプトは、部分ではなく全体の成果を最大化する視点を提供するものです。新しい製造のあり方では、部分の働きが多少劣っていても構わないと考えます。成果を生むのは全体のプロセスだからです。
全体に焦点をあてて最大成果を生み出すことが新しい製造の視点なのです。
新しい製造においては、マネジメントの在り方も変わってきます。部分を超えた全体を意識することが、ものづくりに関わる全ての人に求められるようになるのです。
製造に携わるすべての人は、全体の成果を意識する人になる必要があります。製造部門のすべての人が、人、原材料、設備、時間の調和に責任をもたなければならないのです。
それは、全員がテクノロジストになる必要があるということにほかなりません。新しい製造を支える人たちは、すべてテクノロジストなのです。
テクノロジストとは、知識労働と肉体労働の両方を行う人のことです。知識労働には、組織の最大成果をあげるために自分の仕事を定義することが含まれます。テクノロジストは、与えられた作業をこなすだけの人ではありません。
自分自身の仕事を任務としてとらえ直し、全体の成果を大きくする責任を強く意識することが求められます。たとえ、工場に勤めている人であっても、原材料の調達から最終消費者が実際に製品を使っているところまでを考え抜くことが求められます。
製造業で働くすべてのテクノロジストは、製造の四つの視点をよく理解しておく必要があります。製造のマネジメントとは、製造業の経営者に求められるものであると同時に全員に求められるものだからです。
そして、企業が従業員の学びを重要視するということは、人間として大切にするということでもあります。
次回 その23「新たな起業家精神の必要性」
著者紹介
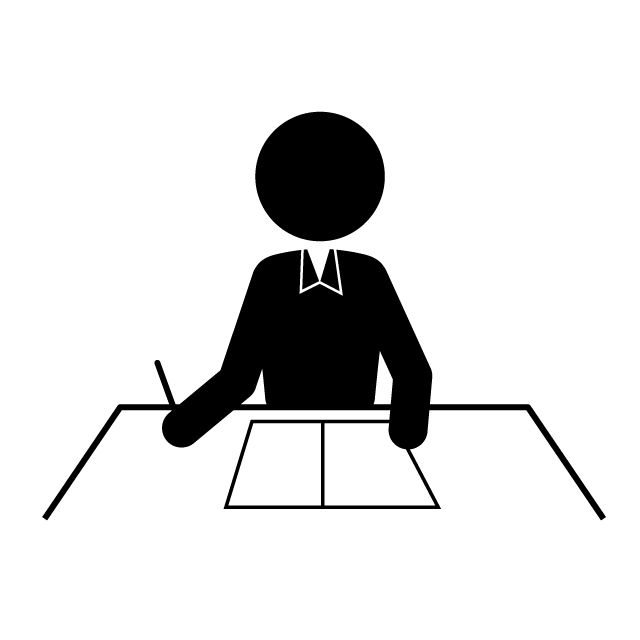 浅沼 宏和
浅沼 宏和
早稲田大学政治経済学部卒、中央大学大学院法学研究科卒、名古屋学院大学 論文博士
「社会制度変容の力学 -内部統制制度・リスクマネジメント・コーポレートガバナンス一体化の論理」
講座に関するご質問、その他通信教育に関するお問合せは、下記担当者までお願いいたします
2025年総合通信教育ガイドについて
ご請求は下記より受け付けております
「一人では変えられないことも、つながれば変わる。」


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる