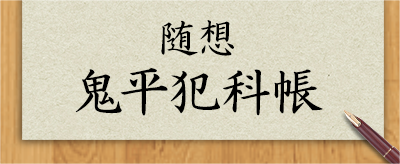随想 鬼平犯科帳
第24回『池波の青春時代』
池波正太郎は昭和10年東京下谷の小学校を出ると、母の勧めで株屋に就職した。店の同輩に中島滋一という文学少年がいて、二人はいつしか二人だけの同人誌『路傍の石』を作り、仕事のあい間に作った俳句、短歌等をそこに発表するようになった。
質札をひろげ五月の更衣かな
これは昭和15年、池波17歳の句で、当時の生活感がよく出ている。
また池波はフランスのサン=テグジュペリの文学が好きになり、その頃彼の小説『夜間飛行』の映画が東京で上映されると、南米で夜間飛をする郵便輸送機の操縦士が暴風雨で方向を見失い、燃料も尽きたので雨雲の上に出ると、美しい月光の海、見とれているとプロペラが止まるというシーンを見て、義務である危険な仕事に献身的に従事し、特に何も求めないという人間の生き方に共鳴をしている。考えてみれば『鬼平犯科帳』も正にそういう生き方をしている鬼平と部下達を描いた小説ではないかと思う。
しかし戦況は厳しくなり、池波は株屋をやめ、17年には小平にあった国民勤労訓練所に入所、その後芝浦の萱場製作所に徴用され、飛行機の精密部品を作る旋盤工となった。最初失敗ばかりしていたが、指導員の水島伍長に「仕事をする前にどこから手をつけるかよく考えろ。手順が一つでも狂えば精密部品はできない」と教えられ、池波は腕ききの旋盤工になっていく。そればかりでなくこの教えは池波が小説や戯曲を書く際にも応用されるようになる。
昭和18年、池波は婦人画報の朗読文学に応募すると、『休日』は5月号選外佳作、『兄の帰還』は7月号入選、『駆足』は11月号佳作、『雪』は12月号選外佳作という結果であった。
昭和19年の1月1日、半年前から萱場製作所の美濃太田工場で指導員をしていた池波は、名古屋の会社に徴用され事務をしている父と名古屋で再会した。父は勤めていた綿糸問屋が倒産したため昭和4年に母と離婚したが、嫌いではなく、父と一晩飲み明かした。なお昭和34年、住所の分らなかった父が死んだが、遺品の中に翌日撮った二人の写真があったという。
父と別れると、父が予感したように召集令状が届き、池波は上京し、母と修善寺に二泊をして別れを告げ、横須賀海兵団に入隊した。そして磯子八〇一空で電話交換手となったが、昭和20年3月10日東京が空襲され、池波が八年住んだ浅草永住町の母の実家が炎上した。母達は無事であったが、休暇を貰い、浅草に立った池波は、
見馴れいし町の姿を目に追いて
廃墟に我は立ちつくしつつ
という歌を詠んでいる。
そして5月、磯子八〇一空は鳥取の美保特攻基地へ移ることになり、池波も電話室長として赴任した。死を前にした人間の眼は特殊なもので、自然や人を見るとやたらに短歌のようなものが浮び、池波達は同人誌『三昧』を月一回作っていた。
そんな中7月7日、母から久方振りに手紙が届いた。読むと、毎日自分のことを案じている母、江戸ものの心を忘れず清く生きているという母、離婚してから苦労して自分を育ててくれた母、三度も焼け出されながら祖母、弟、叔母等を養うため今も東京で一生懸命働いている母がいとおしく、
爆弾の下に横たう国原に
母と生きなむ力の限り
と詠む池波であった。
7月22日母より再度手紙があり、あの廃墟と化した浅草の町で例年通りほうずき市が立ち、四万六千日の行事が行われたことを知り、池波は生きる勇気が湧いてくるのであった。
敗戦後母の許へ帰った池波は、昭和21年読売新聞の演劇文学賞に応募し、戯曲『雪晴れ』で選外佳作を取り、ここから脚本家そして小説家への道が開け始める。


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる