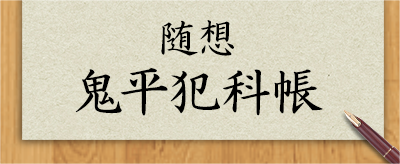新鬼平随想録
第58回「秘密と越中・井波(2)」
長編時代小説「秘密」(文春文庫)には、越中・井波関係の長い記述が5ヶ所もある。先ずは1番目の原文とその備考をお読みいただきたい。
[原文](前略)
「おたみ……」
「あい?」
このとき、片桐宗春は何故、つぎのようなことをおたみに尋ねたのか、自分でもよくわからなかったが、それにはそれで、宗春の脳裡に一種の潜在意識がはたらきかけたのであろう。
宗春は、こういった。
「おたみ。お前、越中(富山県)の
「そんなところ、知りませんよう」
「そうだろうな」
「私の生まれは、葛飾の
宗春は、沈黙した。(後略)
(「秘密」文春文庫233頁)
[備考]最初に、粗筋で述べた様に、宗春は兄が千住で父と同様医者をしていることを知ったが、その2日後におたみと逢い引きをする。この会話はその際に交わされたものである。
次に宗春がおたみに、越中の井波というところを知っているかと尋ねたのは、粗筋で触れた様に、彼がかつて越中・井波へ逃げた時、父の友人の医者に後継ぎになって、井波の人達を
最後に宗春はおたみに自分の秘密を一切話していなかったし、この時も、その秘密の一部である井波を説明する気持がなく、沈黙を守った。しかしこの沈黙には、おたみが初めて天涯孤独の身であることを知り、そんなおたみを絶対に幸せにするという新たな決意も隠されていたに違いない。
続いて2番目の原文とその備考をお読みいただきたい。
[原文](前略)
「おたみ……」
「はい?」
「お前、いつでも、大むらを出られるか?」
「……?」
「出て、私と一緒に、旅へ出る気になれるか?」
「うれしい。先生と一緒に?」
「そうだ。行先は遠い国だぞ。それでもよいか?」
「はい」
いささかもためらうことなく、おたみは強くうなずいた。
うなずいて、
「泣くな」
「で、でも……こんな、しあわせが待っていてくれるなんて……」
「しあわせになるか、どうか、それはわからぬ」
「いいのです。地獄へ落ちたって、先生と一緒なら……」
おたみは、借金をこしらえて[大むら]へ奉公に出たのではないし、いままで何の迷惑もかけてはいない。
「いざそのときになれば、私から大むらのあるじへ手紙を残しておこう。ただし、お前が出るときは黙って出るのだから、いまのうちに仕度をしておくがよい。荷物は小さく……よいか、小さな荷物だぞ」
「うれしい、先生」(後略)
(同 295-296頁)
[備考]最初に、粗筋で書いた様に、その後宗春は逃げ隠れせず、医者として生きようと決心し、髪型も
次におたみは、宗春の最初の質問で、なぜ大むらを辞めるのか分からなかった。しかし第2の質問で、一緒に旅へ出るためと分かり、嬉しかったが、どこへ行くのか分からなかった。そして第3の質問で、一緒に越中・井波というところへ行って暮らすことが分かったので、ためらうことなく、はいと、強くうなずいたが、すぐ、こんな幸せはない、先生と一緒なら地獄に落ちてもいいという想いが込み上げてきて、おたみは宗春にたしなめられても、むせび泣くのであった。
なお、3番目以下の原文と備考は次回でお示しするので、是非続けてお読みいただきたい。
(続く)


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる