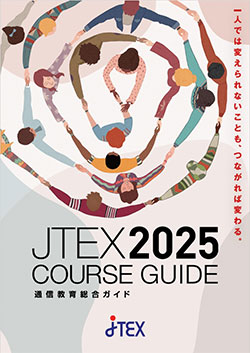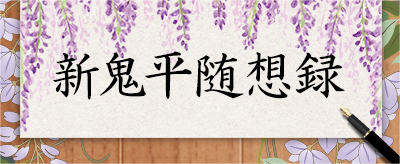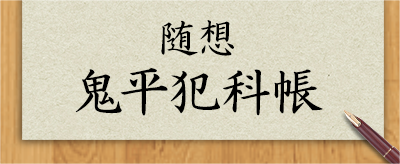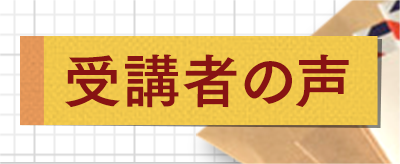メールマガジン
2026年度 通信教育総合ガイドが間もなく完成します!/連載:ものづくり人のためのドラッカー[その40]

*2025年11月6日(木)
気がつけば日脚もめっきり短くなり、冬の訪れを感じております。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日は、
- 2026年度の通信教育総合ガイド
- 「ものづくり人のためのドラッカー」その40
について、ご案内いたします。ぜひ最後までご拝読いただければ幸いです。
【もう少しお待ちください】
通信教育総合ガイドが間もなく完成します!
例年ですと、すでに皆様のお手元に届いている時期かと思いますが、本年度については準備にお時間を頂いております。大変申し訳ございません。
納品については11月下旬を予定しております。
従来からご活用いただいております既存講座につきましても、動画教材や電子ブック対応、Webテスト付き…等、更なる改善を進めております。
皆様のお手元に1日でも早く通信教育総合ガイドが届くよう、順次準備を進めております。今しばらくお待ちください。 “ものづくり人“とは、ものづくりに関わる、経営者、技術者・技能者、営業・管理部門までのすべての人を、そう呼んでいます。
また、教育全般のお問い合わせなども、お気軽にご相談ください。
様々な事例をもとに、最適な御提案をさせていただきます。
新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」
~イノベーションは天才のひらめきではなく、明日に向けた仕事である
著者 浅沼 宏和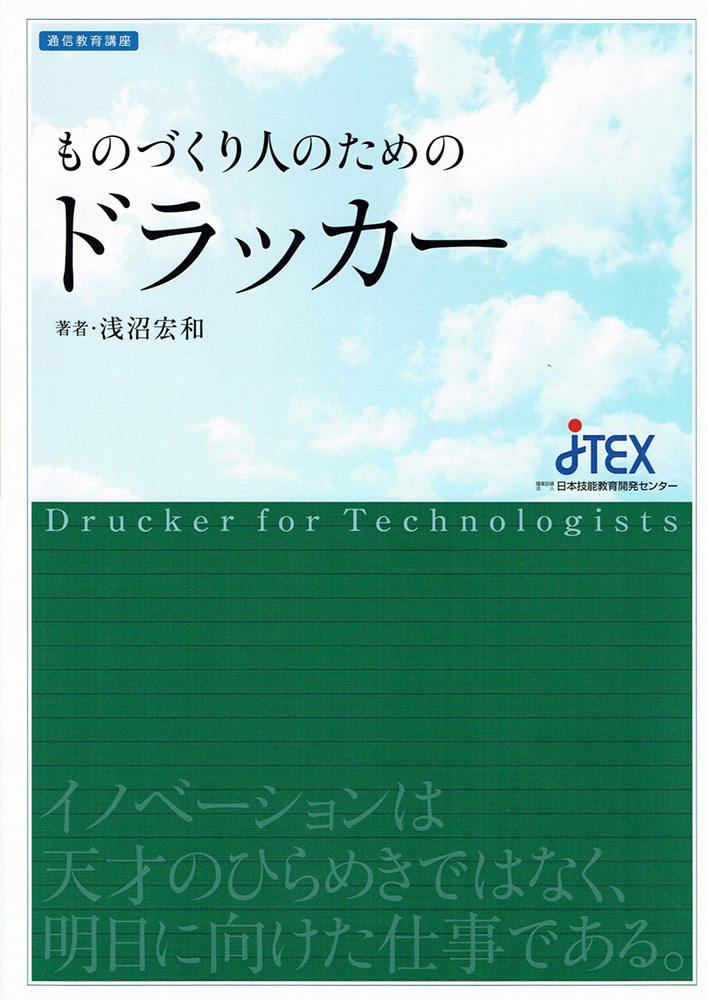
この連載はドラッカーの11冊の著書からリベラルアーツとしてのドラッカーをまとめたものです。
どこかに、役に立つ一言が含まれていることと思います。
ぜひ、ご愛読ください。
その40 企業の「社会的責任」二つの視点
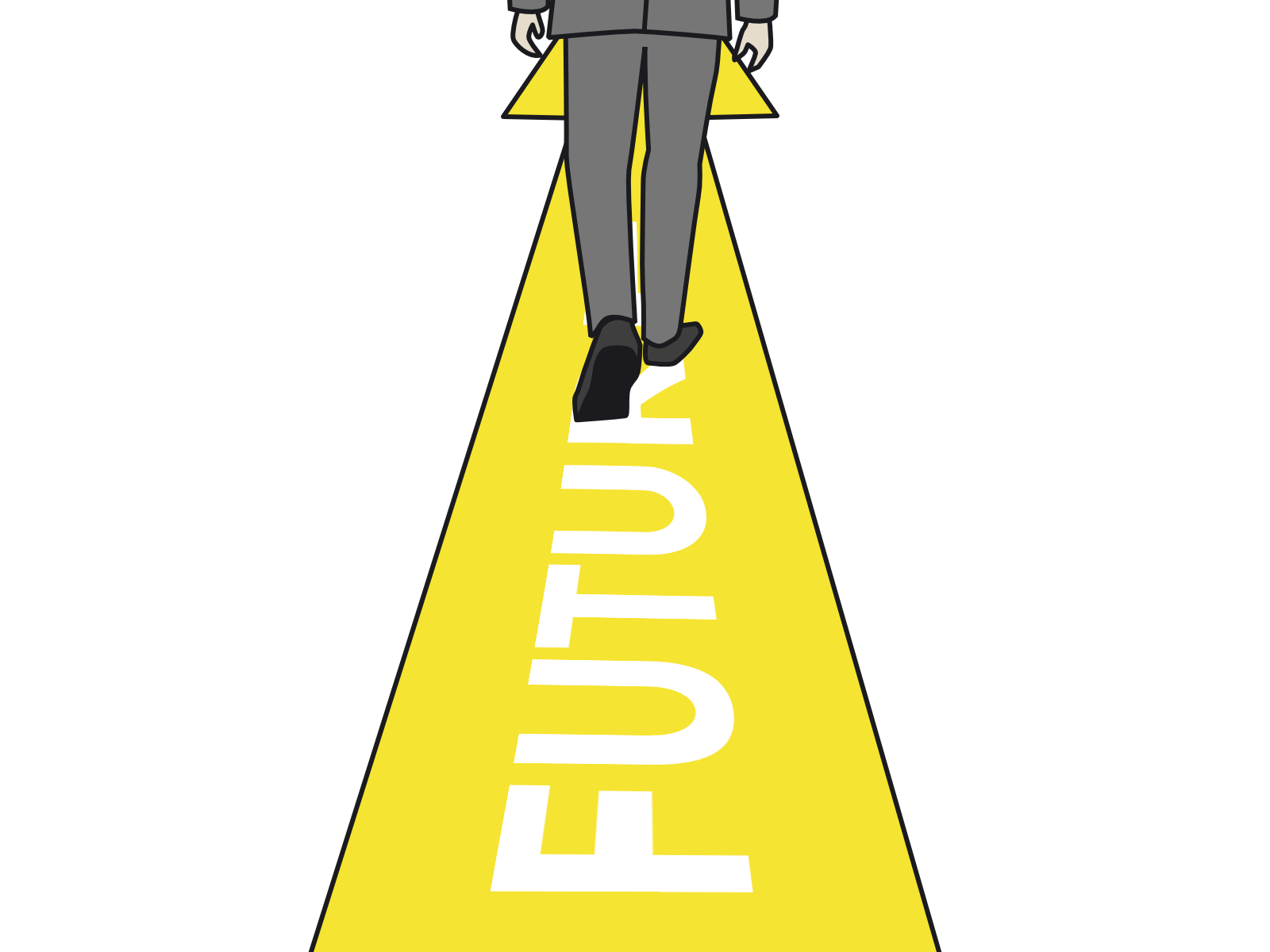
ドラッカーは、企業の社会的責任に早くから注目していました。企業の社会的責任は、事業の成果に、悪くも良くも影響を与えるものですから、これを理解することが大切です。
企業の社会的責任((Corporate Social Responsibility : CSR)については、現在でもいろいろな議論があります。しかし、ドラッカーは「企業が第一に考えるべきことは、自社が行ったことについての責任である」と明確です。
技術についてのマネジメントはこの点も重要であり、たとえば、環境問題について企業が社会的責任を負うべきであるとの論理もここから導かれます。
製造に伴う環境への影響は、いわば技術の副次的影響です。それ自体が顧客への貢献となっていない以上、環境への悪影響はムダでありコストなのです。反対に、環境への負荷を削減できる場合は、それが利点となり、成果を生む可能性が出てきます。
1.野獣の原則
-
ドラッカーは、社会的責任(CSR)を考えるために「野獣の原則」というわかりやすい基準を示しています。
ライオンのような危険な動物の飼い主は、もしも動物が逃げた場合には責任があります。逃げた理由が不注意によるか、不測の災害によるのかは関係ないのです。なぜならば、ライオンのような野獣が狂暴であることは、最初からわかっていることだからです。
つまり、「自分が知っていたことから引き起こされた事態については、たとえどんな理由があったとしても責任がある」ということなのです。
企業の不祥事のニュースなどでは、「想定外の出来事が起こった」などと責任逃れとしか受け取れない発言をして失敗したケースがよく見受けられます。「野獣の原則」をよくよく理解していれば、大きな失敗をしないですむのです。
もしも自社が社会的な問題を引き起こした場合には、次のような行動が求められるでしょう。
・自社に責任があることを明確に認める
・問題発生の状況についてきちんと説明する
・今後の具体的な対応について説明する
そして、問題発生時にこのような手順を踏まなければいけないことから逆算して、日常の業務におけるルールを決めておく必要があるのです。その前提となるのが「野獣の原則」です。
2.共通価値の創造
-
「野獣の原則」は、企業の社会的責任のネガティブな面を扱うものです。しかし企業の使命は、本業において成果をあげて社会に貢献することです。ドラッカーは、社会的責任のこうしたポジティブな側面にも注目していました。
社会の困りごとやニーズの中から事業機会を見出すことこそ、社会的責任を果たすことなのです。
SDGsの流れから、こうした積極的な社会的責任の考え方が、最近では重視されるようになっています。長期的な観点から社会に役立つ価値ある商品サービスの開発、バリューチェーンの見直しによる環境影響の削減、産業の土台となる地域社会発展への貢献といった取り組みを、経営戦略として位置づけようとする考え方が広まってきています。こうした考え方を「共通価値の創造」(Creating Shared Value : CSV)といいます。
このように社会的責任については「野獣の原則」に代表される消極的な面への対応と、SDGs、CSVのような積極的な社会貢献の視点があることを技術のマネジメントの側面でもよく理解しておきましょう。 次回 その41「変化の先頭に立つチェンジ・リーダー」
著者紹介
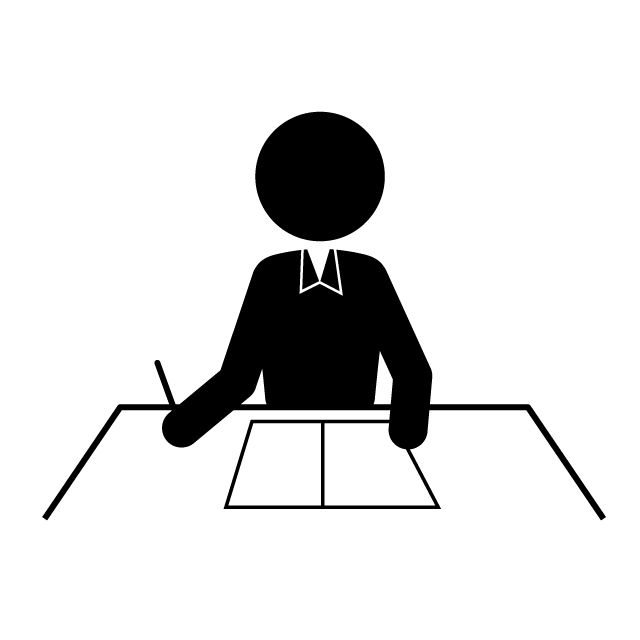 浅沼 宏和
浅沼 宏和
早稲田大学政治経済学部卒、中央大学大学院法学研究科卒、名古屋学院大学 論文博士
「社会制度変容の力学 -内部統制制度・リスクマネジメント・コーポレートガバナンス一体化の論理」
講座に関するご質問、その他通信教育に関するお問合せは、下記担当者までお願いいたします
2025年総合通信教育ガイドについて
ご請求は下記より受け付けております
「一人では変えられないことも、つながれば変わる。」


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる