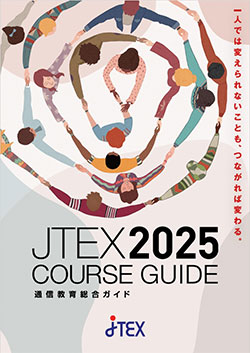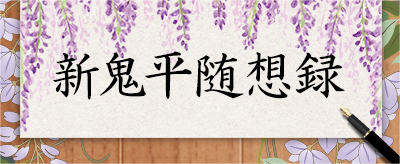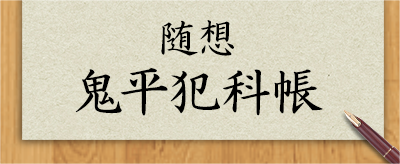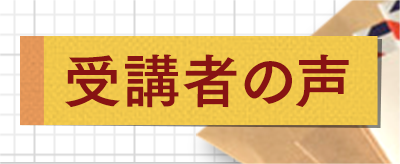メールマガジン
新入社員のこれからにスパイスを…/連載:ものづくり人のためのドラッカー[その12]
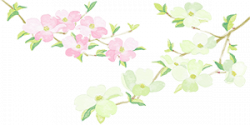
*2025年4月24日(木)
本日は、
- イマドキ新入社員の続き、Part2
- 新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」その12
について、ご案内いたします。ぜひ最後までご拝読いただければ幸いです。
新入社員のこれからにスパイスを…
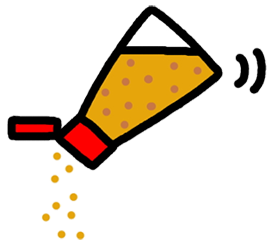
第2弾 普通に使う言葉が若者には通じない!?
ランチ1,000円弱や3時10分前の感覚が…それに続く第2弾として皆様に質問させていただきます。

-
【1時間強】って皆様は何分をイメージされますか?
65分~70分程度を想定される方が多いかと思いますが、
イマドキ若者の思考は、100分程度を想定されるようです!
今まで普通に使用していた言葉が、思わぬ誤解を招く時代に…
質問にて
「この仕事あとどのくらいかかりますか?」に対して、
「1時間強」と伝えた際、
「まだまだかかるのか」と思ってしまい、生産性やモチベーションが下がる可能性があるとイメージする事は、迎え入れる側として必要な事ではないでしょうか。
<新入社員の傾向とは>
※昨年同様大きな変化はありません
現在は、マナーやスタンスよりも、報連相、PDCA等基礎行動を身につけたいと思う割合が高くなっているようです。インプット型の方が、仕事に直接的に役立ち・効率的だと思っている傾向の表れだと推測できます。
-
ポジティブ傾向としては…
★真面目で素直
★必要だと理解した際への柔軟な取り込み
★強い承認欲求 …他人からの評価がモチベーションとなる
★客観的な判断
★同世代と(だけ)の高い関係構築
-
ネガティブ傾向としては…
☆対面コミュニケーション …苦手意識
☆報連相は知っている …が、失敗しそう・したことへの対応が遅い
☆自ら一歩前へ出ようとする行動 …あえて取らず
☆周囲からどう見られるか、どういう行動が適切か …あまり気にせず
☆自己完結 …手の届く情報で済ませる
例えば、LINEやチャットでスムーズなコミュニケーションが取れているのに、
対面での会議でなかなか発言できず、「顔を見ない方が話しやすい」という理由からオンラインミーティングでカメラOFFする新入社員もいます。
このような昨今の生活環境の変化により、対面でのコミュニケーションに苦手意識を持ってしまい、その結果なかなか心を開けない社員も増えてきているようです。新入社員の育ってきた環境をほんの少し考慮し、好まれるコミュニケーションスタイルを知っておくというのも、マネジメントにおいてマイナスにはならないと思います。

<新入社員の5つの特徴>
※昨年同様大きな変化はありません
【自己肯定感】
自己肯定感が低いために
「相手が挨拶をしてくれなかったのは、自分の価値が低いからだ」
「相手が沈黙してしまったのは、自分が上手く話せなかったからだ」
「周りが自分の意見を聞いてくれないのは、受け入れられていないからだ」
といったように、直接的には影響していないことにまで自分のせいだと感じる傾向があります。
そのため職場において、何か大きな失敗をした時や、上司から叱責を受けた時など、手厚いケアが必要になります。
【報連相】
報告・連絡・相談の「報連相」は社会人としての基本とされていますが、他人から自分はどのように思われているかを気にし過ぎてしまい、相手に自発的な働きがけが苦手です。
高い情報収集力の自信から、相談せずに周囲の意見を聴く機会が減らしてしまい、自身の偏った思い込みで進めてしまう可能性がでてしまいます。
【これぞ正解】
ビジネスにおける唯一の正解は、「正解がない」ということですが、それに対する恐怖心があります。
一方で、その情報処理能力には目を見張るものがあり、興味を持つとそこから関連する情報を見つけ出すことに非常に長けています。
更に、難しい状況をキーワード化して整理することがとても上手です。
【言われたことは…】
人よりも頑張った結果、嬉しかった、評価されたという実体験が減っているため、「間違いないよう・否定されないよう・無難に安全に正しいことをやる」ことで、自身を守ってきました。
逆に指導側が一生懸命関わってくれていれば、「役に立ちたい!」という思いで、より頑張ることができるという強みを持っています。
【貢献】
社会的な問題を解決できる人財になる、そのために難しい仕事に挑戦したいというよりは、目の前の人に感謝してもらえることで世のため人のために役に立っている感覚、人と繋がっている感覚が欲しい…貢献の言葉の根底に「繋がっていたい」という思いが見えます。

「社会の価値観」と「会社の価値観」
この2つの価値観についてしっかりすり合わせを行うことが必要になってくると思われます。
定期的に価値観のズレがないか、あるとすれば会社の方針はどのよううにしていくかを明確にすることで、社員の見えない不満感にも気が付くことができるのではないでしょうか。
- 内定者通信教育
- 新入社員研修
- 新入社員通信教育
- 新入社員フォロー研修
- 新入社員フォロー通信教育
各、テーマごとのお打ち合わせや、ご相談をいただいております。
通信教育だけでなく、外部講師を招いての講師派遣においてもお客様より「変化」を求められ、セカンドオピニオン的なイメージで研修依頼の相談を受けております。
少しでも気になる事があれば、すぐにご相談いただければと存じます。


新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」
~イノベーションは天才のひらめきではなく、明日に向けた仕事である
著者 浅沼 宏和
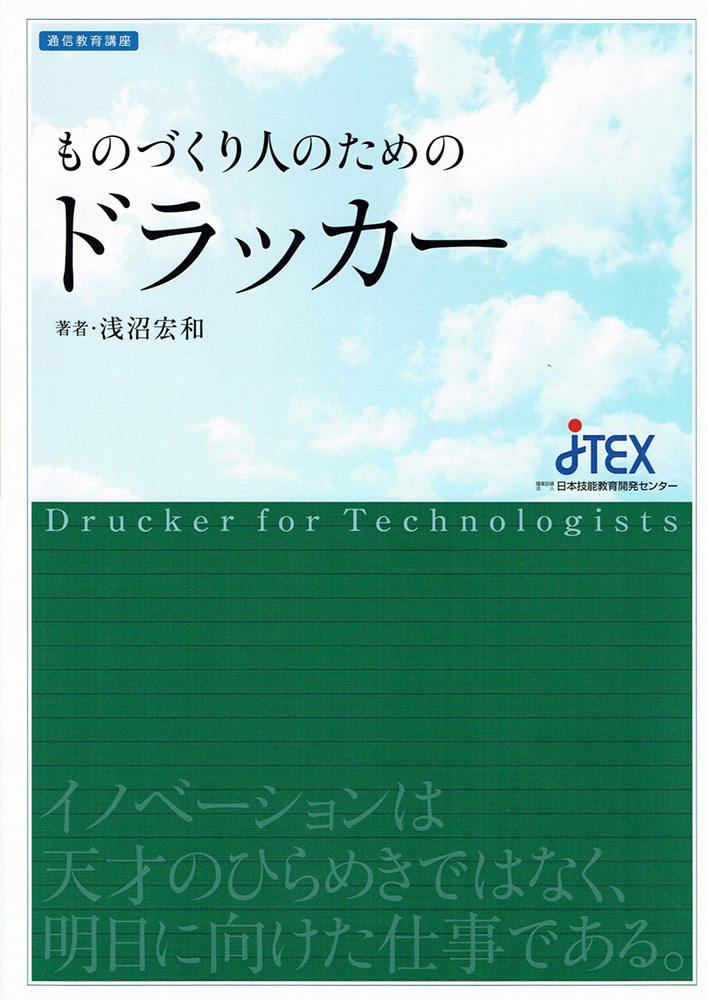
“ものづくり人“とは、ものづくりに関わる、経営者、技術者・技能者、営業・管理部門までのすべての人を、そう呼んでいます。
この連載はドラッカーの11冊の著書からリベラルアーツとしてのドラッカーをまとめたものです。
どこかに、役に立つ一言が含まれていることと思います。
ぜひ、引き続きご愛読いただきたく、連載を開始いたします。
その12 知識労働の生産性
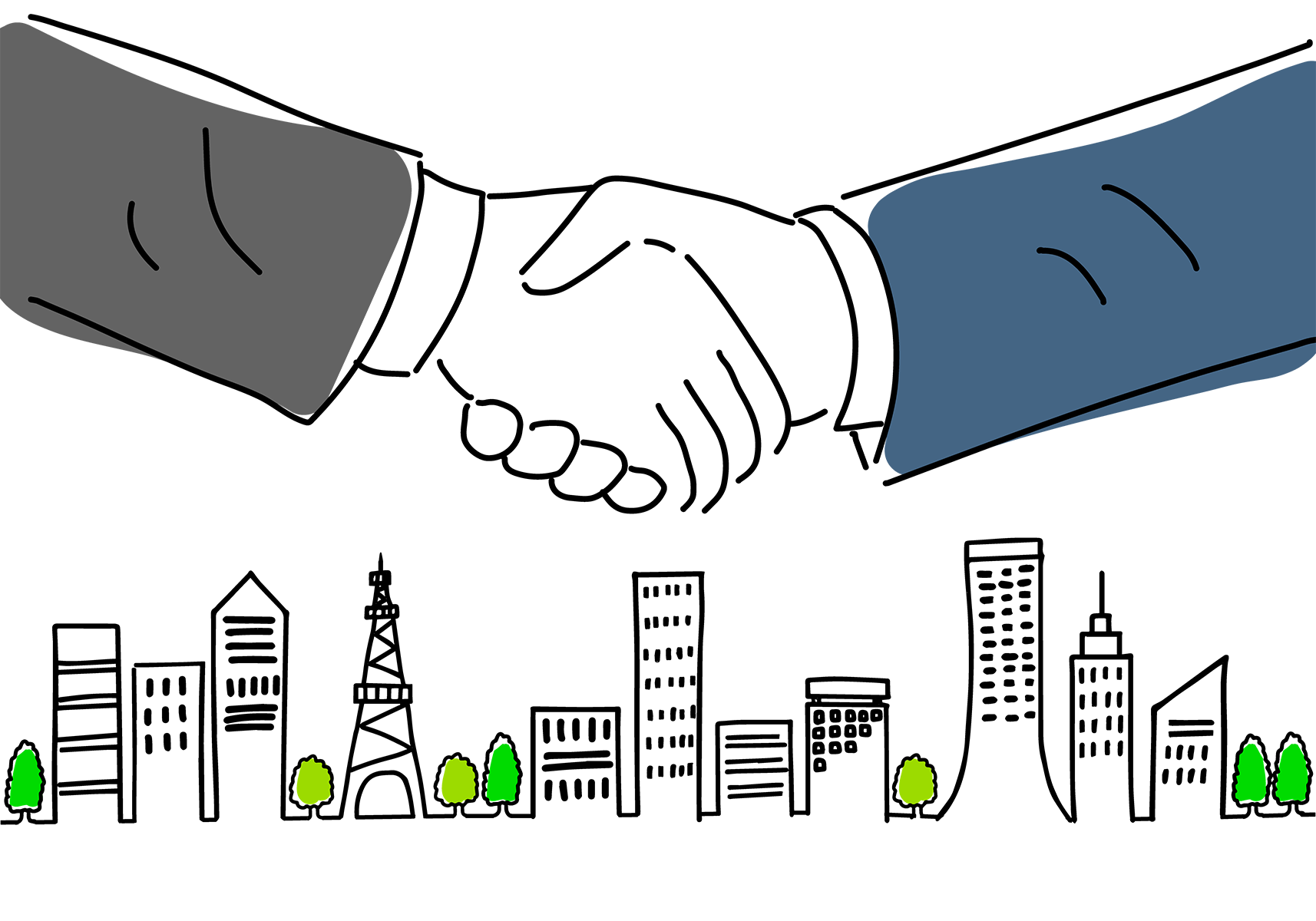
ドラッカーは、知識労働の生産性向上の条件として、次の6点をあげました。
-
・条件1 仕事の目的を考える。
・条件2 働く者自身が生産性向上の責任を負い、自らをマネジメントする。
・条件3 継続してイノベーションを行う。
・条件4 継続して学び、人に教える。
・条件5 知識労働の生産性を「量」ではなく、「質」の問題としてとらえる。
・条件6 知識労働者は組織のコストではなく、資本財であるととらえる。
これら6点のうち、条件6以外の5つは、肉体労働の条件とちょうど反対になっています。
肉体労働では何をすべきかが明白ですが、知識労働は違います。まず、目的を定義しなければなりません。
また、肉体労働でも質は重要ですが、それは制約条件にすぎません。これに対して知識労働では、質は仕事の制約条件ではなく、仕事の本質として位置づけられているのです。これは決定的な違いといえるでしょう。
ドラッカーは教師の仕事を例にとり、生徒の数ではなく、何人の生徒が本当に理解できたかで評価されるべきと説明しています。病院の検査業務でも検査の数ではなく、検査の質であり、設計や事務の仕事も同様です。知識労働の生産性は、量ではなく質の問題なのです。
ドラッカーは、知識労働の質について、「最高ではないにしても最適を基準にしなければならない」と指摘しています。
そして知識労働の生産性を高めるためには、知識労働者自身が仕事をマネジメントすることが必要です。
成果をあげるために、自分自身でより良い仕事のやり方を工夫し、段取りを組んで仕事をする必要があります。
成果を上げるための習慣の一つが貢献意識を持つことです。最大成果をあげる責任の自覚が大切なのです。それがあって、はじめて自らの仕事をマネジメントすることができます。
もう一つ、イノベーションも知識労働に特有の考え方です。知識労働では知識が知識を生み出す連鎖が続きます。
つまり、知識がどんどん発展する可能性を持つのです。知識労働では学び続けなければ、いずれ成果をあげることができなくなってしまうのです。
2022年から「人的資本経営」という言葉が出て、人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値の向上につなげる経営のあり方を日本企業もめざすようになりました。
ドラッカーは2005年に亡くなっていますので、その遥か前から、成果をあげる能力を身に付けた知識労働者は、企業にとって資本財であると主張していたのです。
次回 その13「知識労働の目的と質」
著者紹介
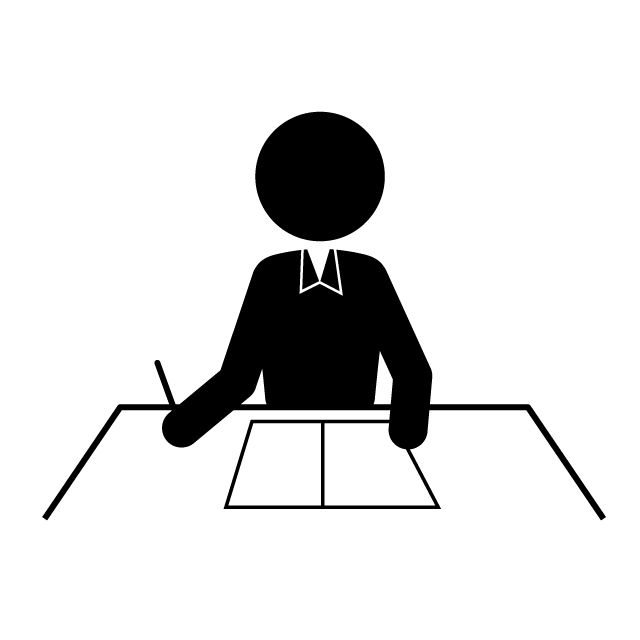 浅沼 宏和
浅沼 宏和
早稲田大学政治経済学部卒、中央大学大学院法学研究科卒、名古屋学院大学 論文博士
「社会制度変容の力学 -内部統制制度・リスクマネジメント・コーポレートガバナンス一体化の論理」
講座に関するご質問、その他通信教育に関するお問合せは、下記担当者までお願いいたします
2025年総合通信教育ガイドについて
ご請求は下記より受け付けております
「一人では変えられないことも、つながれば変わる。」


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる