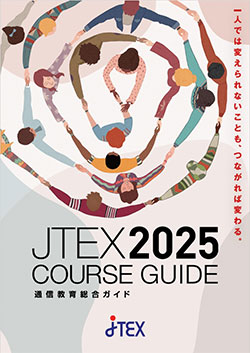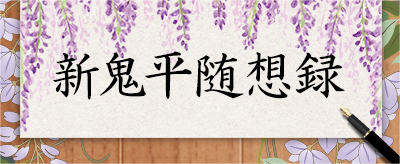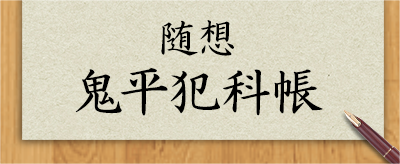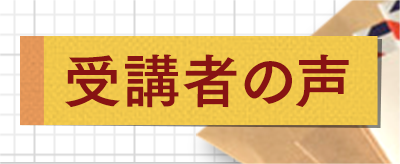メールマガジン
新規開講講座「問いをたてる技術を磨く~AI活用対応『質問力・検索力アップ講座』」 /連載:ものづくり人のためのドラッカー[その3]
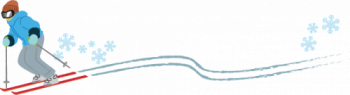
*2025年2月6日(木)
皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日は、
- 新規講座「問いをたてる技術を磨く~AI活用対応『質問力・検索力アップ講座』
- 新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」その3
について、ご案内いたします。ぜひ最後までご拝読いただければ幸いです。
新講座が開講します!
「問いをたてる技術を磨く~AI活用対応『質問力・検索力アップ講座』」
いまなぜ質問力・検索力なのか?
インターネットが普及し、パソコンやスマートフォンを当たり前に使用するようになった今、私たちは大量の情報を簡単に得られるようになりました。仕事のツールとしてICTや生成AIなどの活用が進み、情報を処理するスピードも格段に向上しています。こうした状況の中で、改めて質問力・検索力の重要性が増しています。

質問力とは?

-
質問力とは、「問いをたてて、相手からの有効な情報を引き出す力」です。
人間相手の場合も、インターネット相手の場合も、生成AI相手の場合もあります。
いずれにしても、良い回答を得るには、良い質問が必要です。
生成AIに聞くときも「質問力」がカギとなります。
この講座では、的確なアウトプットを得るための、質問力を磨いていきます。
検索力とは?

-
検索力とは、「必要な情報を探し出す力」です。
大量のデータの中から必要な情報を探し出す力の重要性が増してきています。
この講座では、電子データを対象とした検索力を磨いていきます。
著者はどんな人?
-
著者はIT関連全般や働き方改革に詳しく、多数の著書を出版している
コミュニケーションと人材を切り口に企業改革を進めるコンサルタントとして活動中です。
システムエンジニアや営業、人事など幅広い分野で活躍された経験をお持ちの先生に、「質問力」「検索力」について、「問いをたてる力」を軸に分かりやすく解説していただきました!

編集者から一言
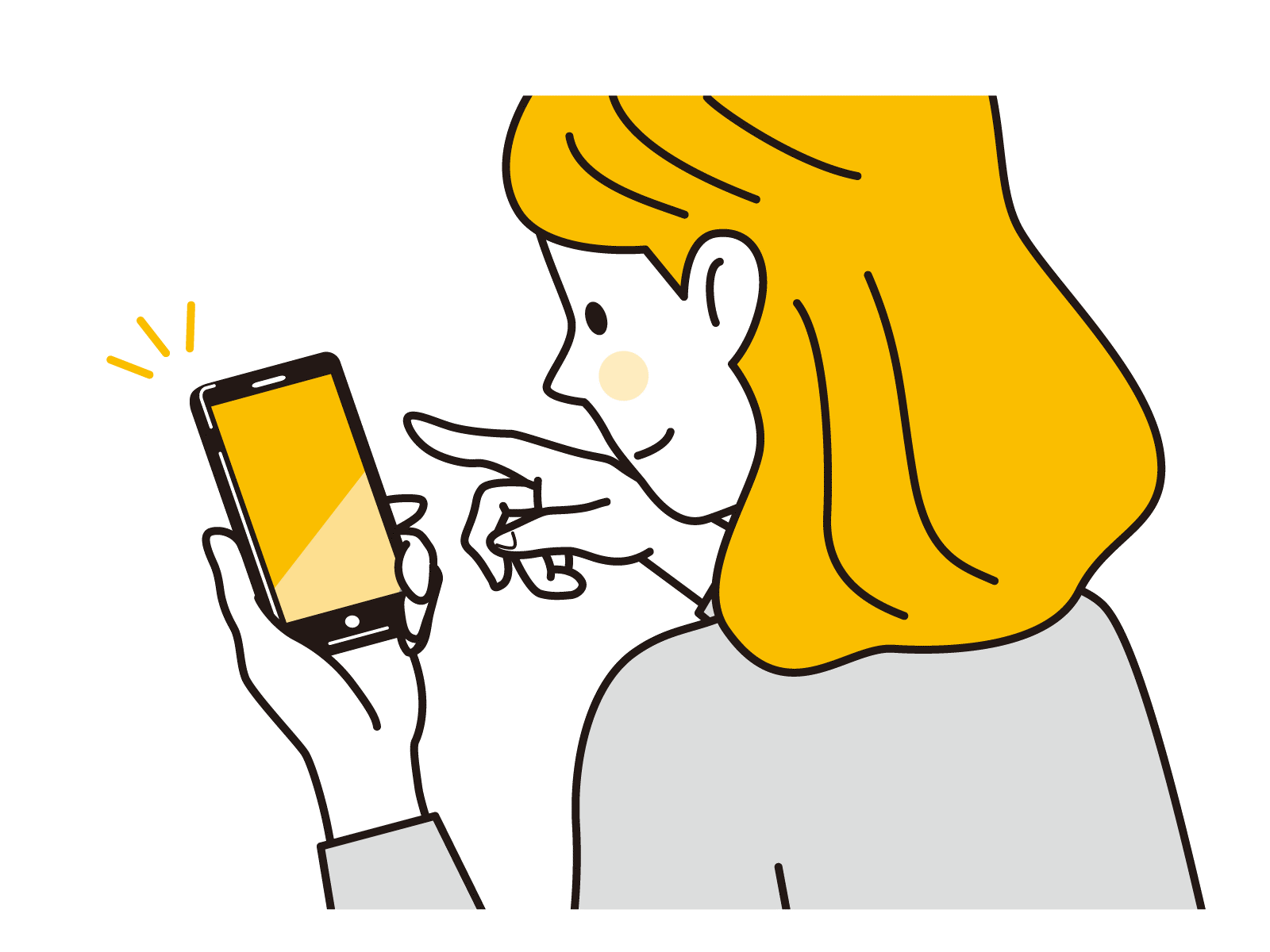
-
スマートフォンが片時も離せない私(皆さんもきっとそのはず…)。
分からないことはすぐにスマートフォンに聞いてしまいます。
調べたいことがはっきりしているときはいいのですが、何を調べたいかもあいまいなときもありますよね。
その分野に詳しい人が調べていきついた結果と、自分が調べた結果に違いがあるときもしばしば。
「どうやって検索するの?」と聞くこともありました。
「問いをたてる」視点からみたこの講座では、対人コミュニケーションから、生成AIを有効活用するシーンまで、さまざまな事例を挙げて「質問力」「検索力」を磨いていきます。
ぜひ、この機会にご検討ください!

新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」
~イノベーションは天才のひらめきではなく、明日に向けた仕事である
著者 浅沼 宏和
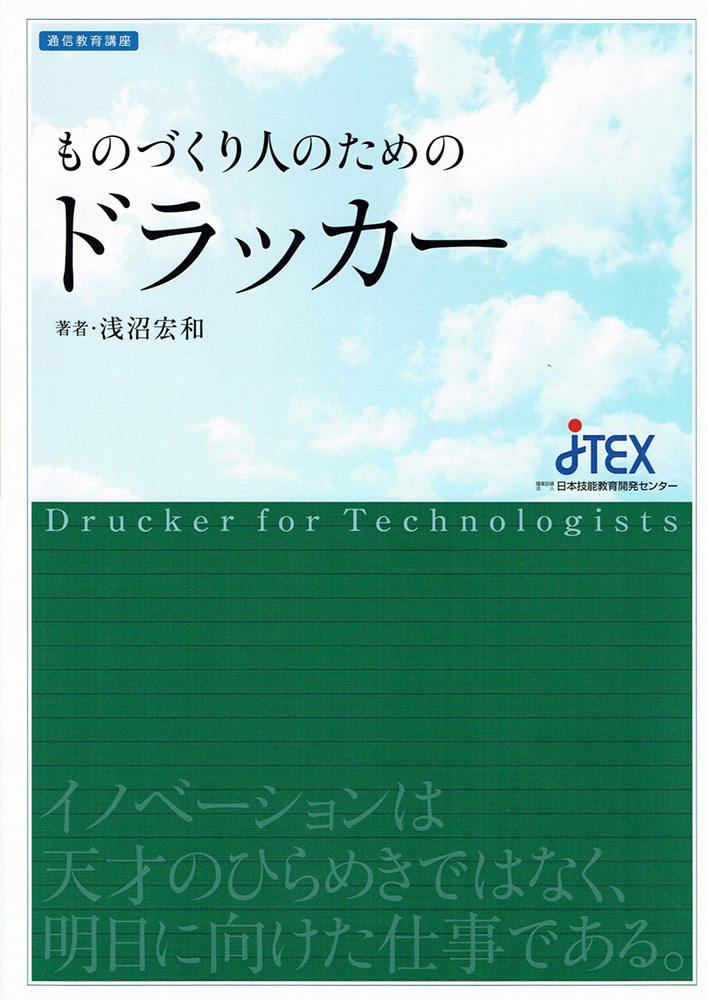
“ものづくり人“とは、ものづくりに関わる、経営者、技術者・技能者、営業・管理部門までのすべての人を、そう呼んでいます。
この連載はドラッカーの11冊の著書からリベラルアーツとしてのドラッカーをまとめたものです。
どこかに、役に立つ一言が含まれていることと思います。
その3 成果の三つの領域と経営戦略の土台
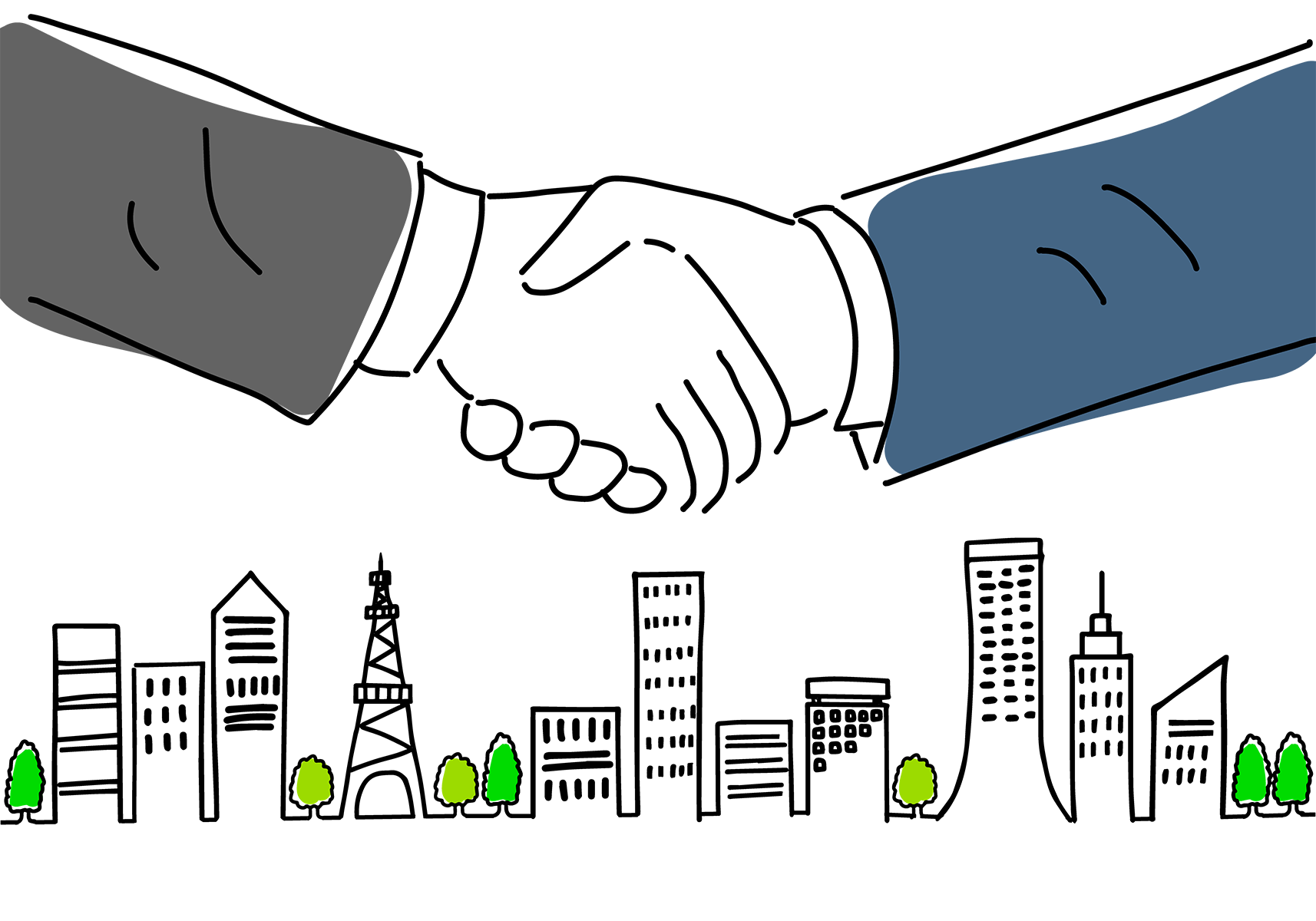
企業の目的は顧客の創造=お客様づくりです。
では、具体的にどのようにすればお客様を増やすことができるのでしょうか。ドラッカーは、顧客の創造とは三つの領域のバランスを取ることで実現されると説明しています。
1.市場・顧客の領域
2.商品・サービスの領域
3.流通チャネルの領域
この三つの領域のバランスが取れていれば業績が良く、バランスが悪いと業績が悪くなります。
ドラッカーは企業がやるべきことを単純明快に整理したのです。それぞれを見ていきましょう。
1.市場・顧客の領域
-
顧客の創造は、市場・顧客の領域のニーズ・期待に応えることで実現されますから、経営戦略は、まずこの領域について考えるところからスタートします。
ドラッカーは「顧客の価値、欲求、期待、現実、状況、行動からスタートしなければならない」といっています。
2.商品・サービスの領域
-
顧客の創造は、市場・顧客の領域におけるニーズや期待に対して、価値・効用を生み出すことで実現されます。
商品サービスは、価値や効用を生み出す手段であり、価値や効用こそが商品・サービスの本質なのです。
日曜大工店でドリル(商品)を購入する顧客は、ドリルそのものではなくて「穴」をあける(効用)道具を買うのです。
商品・サービスを生み出す前に顧客のニーズや期待をとことん考え理解しなければなりません。
3.流通チャネルの領域
-
顧客の創造は、商品・サービスを市場・顧客への届ける流通チャネル(ルートや手段)が必要です。
流通業者や運送業者、事業場のパートナー、各種メディア・ネット媒体、キーマンなど、価値を顧客のニーズに届けるためのあらゆる手段といったように幅広くとらえましょう。
どれほど素晴らしい価値を創造しても、それが顧客にまで届かなければ意味がありません。
ドラッカーは当初、流通チャネルを「第二の顧客」と呼んでいましたが、後には「第一の顧客」と表現するほど重視していました。
ものづくりとは、製品をつくるのではなく、価値を創造すると考えるべきです。
製造とは、工場内で良い製品をつくる活動ではなく、顧客の創造という成果を生み出すためのものなのです。
では、具体的にはどのような視点で考えるべきでしょうか。
ドラッカーは私たちに馴染みのある言葉である「ヒト、モノ、カネ」の三つの経営資源を最大限に活用し、三つの成果領域のバランスを取って顧客を創造することが経営戦略の目的だといいます。
三つの経営資源のうち、最も重要なものは「ヒト」です。
ドラッカーは「ヒト」は時間と知識であると説明しています。
「時間」こそが成果をあげるための最大の制約条件です。
時間は、借りたり、買ったり、貯蔵したりできず、投入できる時間の範囲内でしか成果をあげることができないのです。
「知識」とは単なる情報ではないのです。ドラッカーは知識とは単なる情報を成果に変える能力であるといっています。
企業が長年蓄積してきた経験、独自に工夫してきた成果をあげるための仕組みに関わるものといえるでしょう。
ドラッカーは「ヒト」という経営資源を時間と知識の二つの要素に単純化して表現することで、具体的な行動の視点を導きやすくしたのです。
「モノ」「カネ」という二つの経営資源はわかりやすいでしょう。
「モノ」は建物、設備、装置、原材料の調達、システムも含み広くとらえましょう。
同様に「カネ」も資金調達だけでなく、在庫削減やコスト削減、不得意分野のアウトソーシングによる投資の節約など広くとらえます。
「ヒト」を時間と知識に単純化し、「モノ」「カネ」を広くとらえることで大きな価値創造に向けた取り組みを考えやすくしたのです。
経営戦略は部分的な活動の計画ではなく、あらゆる経営資源をより大きな成果に向けて総動員する全体計画と考えなければなりません。
そうした視点をドラッカーは「生産性」と呼び、三つの経営資源と生産性は、ドラッカーの経営戦略の土台なのです。
次回 その4「ピラミッドをつくる組織とマンモスを狩る組織」
著者紹介
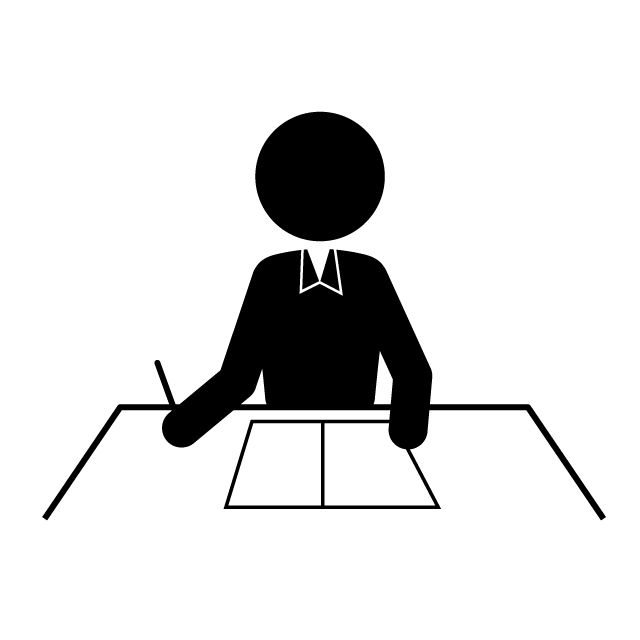 浅沼 宏和
浅沼 宏和
早稲田大学政治経済学部卒、中央大学大学院法学研究科卒、名古屋学院大学 論文博士
「社会制度変容の力学 -内部統制制度・リスクマネジメント・コーポレートガバナンス一体化の論理」
講座に関するご質問、その他通信教育に関するお問合せは、下記担当者までお願いいたします
2025年総合通信教育ガイドについて
ご請求は下記より受け付けております
「一人では変えられないことも、つながれば変わる。」


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる