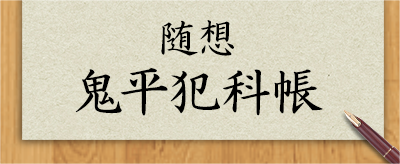随想 鬼平犯科帳
第1回『おれの弟』
私は池波正太郎の小説が大好きである。彼の父方の先祖が郷里の越中井波の出身であるからでもあるが、その小説の奥底に流れる人生観に共鳴するからである。その人生観が最もわかる小説が、昭和43年の鬼平犯科帳『谷中いろは茶屋』(文春文庫2巻)である。
粗筋をいうと、鬼平の部下木村忠吾が役目をさぼって谷中のいろは茶屋で遊蕩を続けるうちに、近所のお寺に急ぎ働きをした墓火の秀五郎一味の一人の居場所をつきとめ、鬼平は一味を武州粕壁で一網打尽にする。一方、墓火は下見のためいろは茶屋に通っているうちに、揚代が無くなった忠吾の話を聞き、相方の妓に十両与え、忠吾が遊べるように計らう。勿論、お互い顔も素性も知らない。そんな事件が落着後、忠吾が親切な人から十両をもらって遊蕩したことを白状すると、鬼平はその人を褒めながら、
善事をおこないつつ、知らぬうちに悪事をやってのける。
悪事をはたらきつつ、知らず識らず善事をたのしむ。これが人間だわさ。
と言うが、これが池波の人生観で、鬼平犯科帳の登場人物は皆そんな人生観で描かれている。
しかし、善悪があいまいなのではない。悪事を働く人を時には許し、限度を超えると絶対に許さない、そんな鬼平犯科帳の世界に胸がすく思いがするのである。
だから、鬼平も悪事を働くことがある。その代表例が、昭和53年の『おれの弟』(文春文庫18巻)である。
鬼平が通った本所の高杉道場の弟弟子の滝口丈助は、小石川の高崎道場の跡目を継ぐことになったが、これに反対の石川源三郎が決闘を申し込んでくる。高田の南蔵院裏の松林へ行った丈助は胸に矢を受けたうえ五人に襲われ、駆けつけた鬼平の腕の中で息絶える。鬼平は若年寄京極備前守に事件を届け出、評定所が調べを始めるが、源三郎の父、将軍御側衆の石川筑後守はこれをもみ消す。
10ヵ月後の翌年春のある日の早暁、源三郎は家来一人と広尾ヶ原を馬で駆けていると、家来が付いてこない。すると前方から塗笠の侍が騎馬で近付き、いきなり棒で突いて源三郎を落馬させる。抜刀した源三郎に、下馬して笠を取った侍は弟の敵討という。それが鬼平と知った源三郎は、父は御側衆なるぞと叫ぶが、「なればこそ尚更に生かしておけぬ」と言って、鬼平は一太刀目に左肘を切り、ついで源三郎の喉笛から首筋にかけて粟田口国綱で切り割った。家来は部下が落馬させ、気絶させており、広尾ヶ原に人影一つ見えなかった。


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる