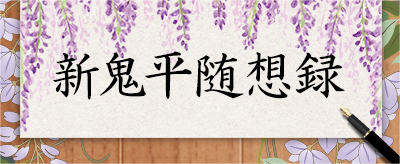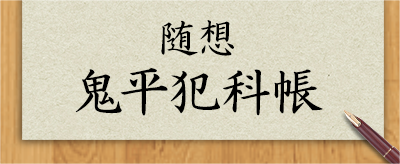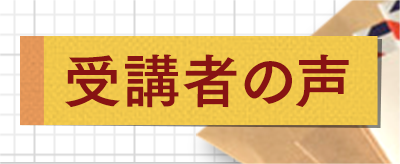メールマガジン
「メンターの基本」セミナー質問と回答/連載:ものづくり人のためのドラッカー[その43]

*2025年11月27日(木)
外を歩くと落ち葉がカサカサと音を立てて、秋の終わりを感じます。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日は、
- 先日行われた「メンターの基本」オンラインセミナーにていただいたご質問と講師からの回答
- 「ものづくり人のためのドラッカー」その43
について、ご案内いたします。ぜひ最後までご拝読いただければ幸いです。
オンラインセミナー「メンターの基本」質問と回答

先日行われた無料オンラインセミナー「メンターの基本」では、たくさんの方にご参加いただきました。
お忙しい中お時間をつくっていただいた皆様、誠にありがとうございました。
当日チャットでご質問いただいた内容につきまして、講師からの回答をご紹介いたします。
メンター制度導入の参考になりましたら幸いです。
質問(1)

-
嘱託社員の活躍の場として、メンターを考えています。概要に賛同していただければ、なのですが、世代間ギャップなどは問題ないでしょうか。

-
テキストで学習いただければ、問題ないよう設計しております。
ただし、近しい年代に比べれば、キャリア観や中長期的目標が一致しない懸念はあります。
開始前のメンターに対する動機付け(会社からの期待を伝える)を推奨します。
質問(2)

-
弊社では、メンターとして総務担当者が四半期に一度面談しています。この運用は、職場内にメンターを設定するように変更した方がよいのでしょうか。

-
目的によります。
総務担当者が面談することの良さもあります。組織リスク(ハラスメントや過度な偏った組織風土による弊害)は人事系社員の方が的確且つ早急に対応できるなど。
先輩社員がメンターになる場合、社内の人脈形成により離職率の大幅減、キャリア観構築の相互支援、学び合う文化の醸成・継承など、より広い範囲での効果は期待できると言えます。
質問(3)

-
メンターは毎年変更した方がいいのでしょうか。何年か続けてもらうのがよいのでしょうか。

-
会社の制度とする場合は、1年単位とすることを推奨します。
双方が継続を希望する場合もありますが、期間を区切ることでメリハリがつきます。
強い希望があれば、会社の施策外として実施する分には自由かと考えます。
質問(4)

-
メンティー側にも教育をした方がよいでしょうか。

-
メンティー側については、制度への理解と心の準備さえできていれば問題ありません。
会社側はそれらを支援するよう、入社導入研修や、メンター制度の開始説明会など、制度について会社側として目的や概要を説明する場を設計ください。
質問(5)

-
業務に直接携わっていない先輩がメンターになるのが好ましいとのことですが、まだ人数が10人程度の会社なので、弊社では難しく、もう少し会社として人数が増えた状態でメンター制度は始めた方が良いでしょうか。

-
あくまで「好ましい」ですので、メンター制度の導入は全く問題ありません。
ただし、相互に人となりがわかる場合、多少のリスクもございます。
メンタリングの考え方をご存知ない周囲が「遠回りな指導の仕方をしている」と、メンターやメンティーをかえって孤立させかねません。
会社からの丁寧な環境整備(周囲の理解を得る)を推奨いたします。
質問(6)

-
メンターに人事・上司への面談共有は不要だとして、面談の記録・チェックシートなどを活用してもらう方がよいでしょうか。

-
テキストに「面談のフォーマット」(何について話すか)は付録がついています。
目的にもよりますが、面談の詳細な記録やチェックシートは必要ではありません。
質問(7)

-
目的の制度設計の項目はどのくらいが目安でしょうか。

-
メンターにテキストを学習いただき、会社として環境整備や開始説明を行えば、下記いずれの目的も達成可能でしょう。
- 「採用コスト低減」
- 「育成コスト低減」
- 「組織リスクの低減」
- 「次世代リーダーの育成」
- 「管理職の負担軽減」
- 「組織風土の改善」
ただし、後の3つは中間や終了後の学習機会を設け、適切に問いを立てること、数代にわたり繰り返しメンティー/メンター経験者が増えることで、より確かな効果が得られます。
メンター制度の導入を検討いただいているご担当者の方の疑問が少しでも解消できましたら幸いです。
メンター制度は、先輩社員が後輩社員の不安や悩みを聞き、サポートする社内制度です。採用活動の難航や短期での離職が増えている中、新人・若手社員の定着において、メンター制度を導入している企業が増えています。
2026年1月開講のJTEX通信教育「新人・若手社員によりそう メンターの基本」では、メンターとしての役割や心構えを認識し、メンタリングの知識や手法を丁寧に解説していきます。この講座をご受講いただきますと、メンターとして自信を持って対応することができるようになります。ぜひ、ご受講をご検討ください!
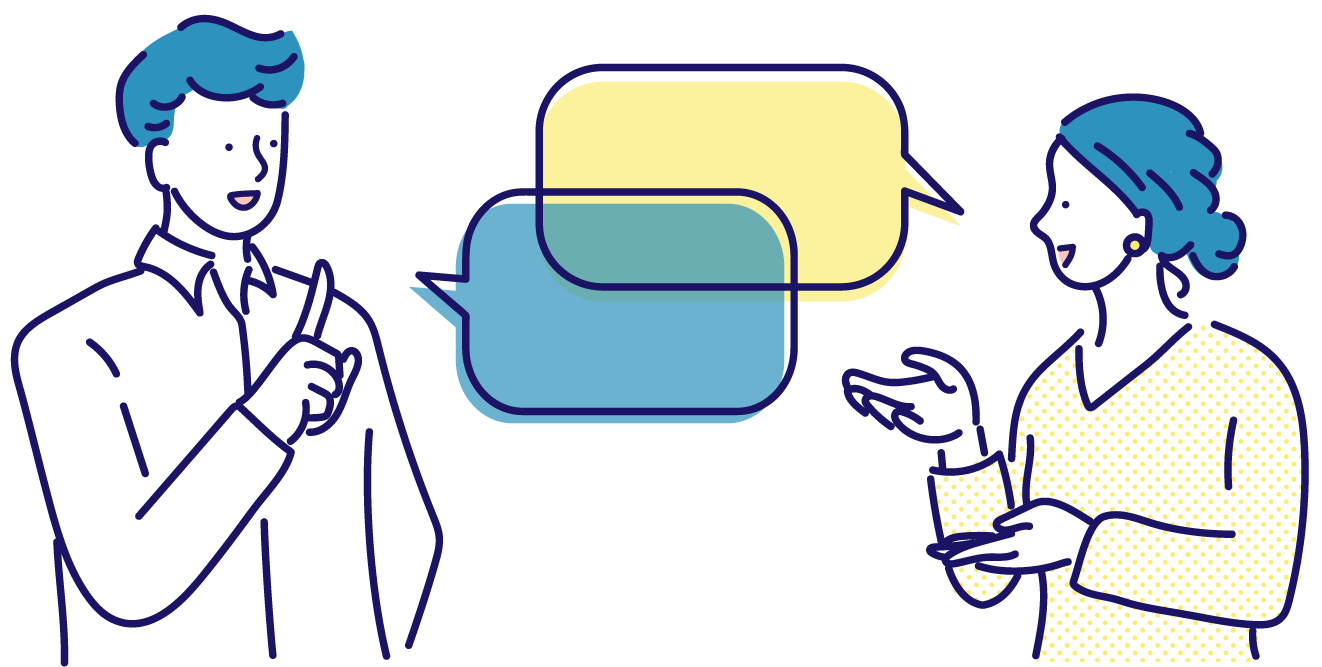
通信教育「新人・若手社員によりそう メンターの基本」
-
・第1章 メンタリングとは
・第2章 メンティーの気持ち
・第3章 メンティーを受け止めよう
・第4章 メンティーの考え整理を支援しよう
・第5章 メンティーに提案しよう
・第6章 メンターこそ学ぼう
・第7章 ケーススタディ
新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」
~イノベーションは天才のひらめきではなく、明日に向けた仕事である
著者 浅沼 宏和
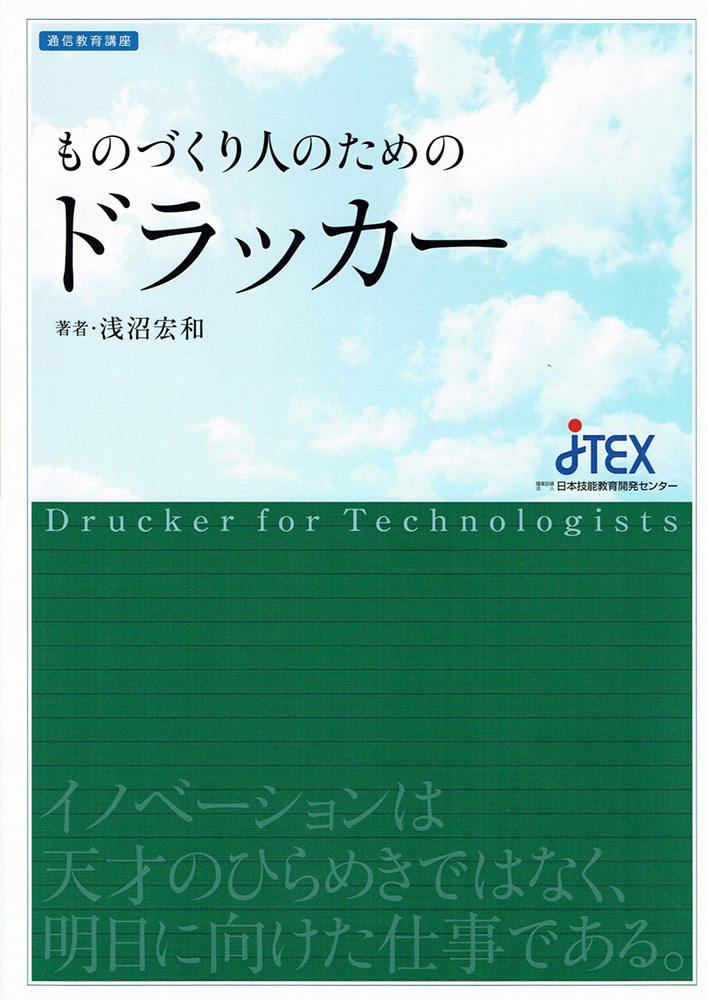
“ものづくり人“とは、ものづくりに関わる、経営者、技術者・技能者、営業・管理部門までのすべての人を、そう呼んでいます。
この連載はドラッカーの11冊の著書からリベラルアーツとしてのドラッカーをまとめたものです。
どこかに、役に立つ一言が含まれていることと思います。
ぜひ、ご愛読ください。
その43 昨日を守り、明日を犠牲にした事例
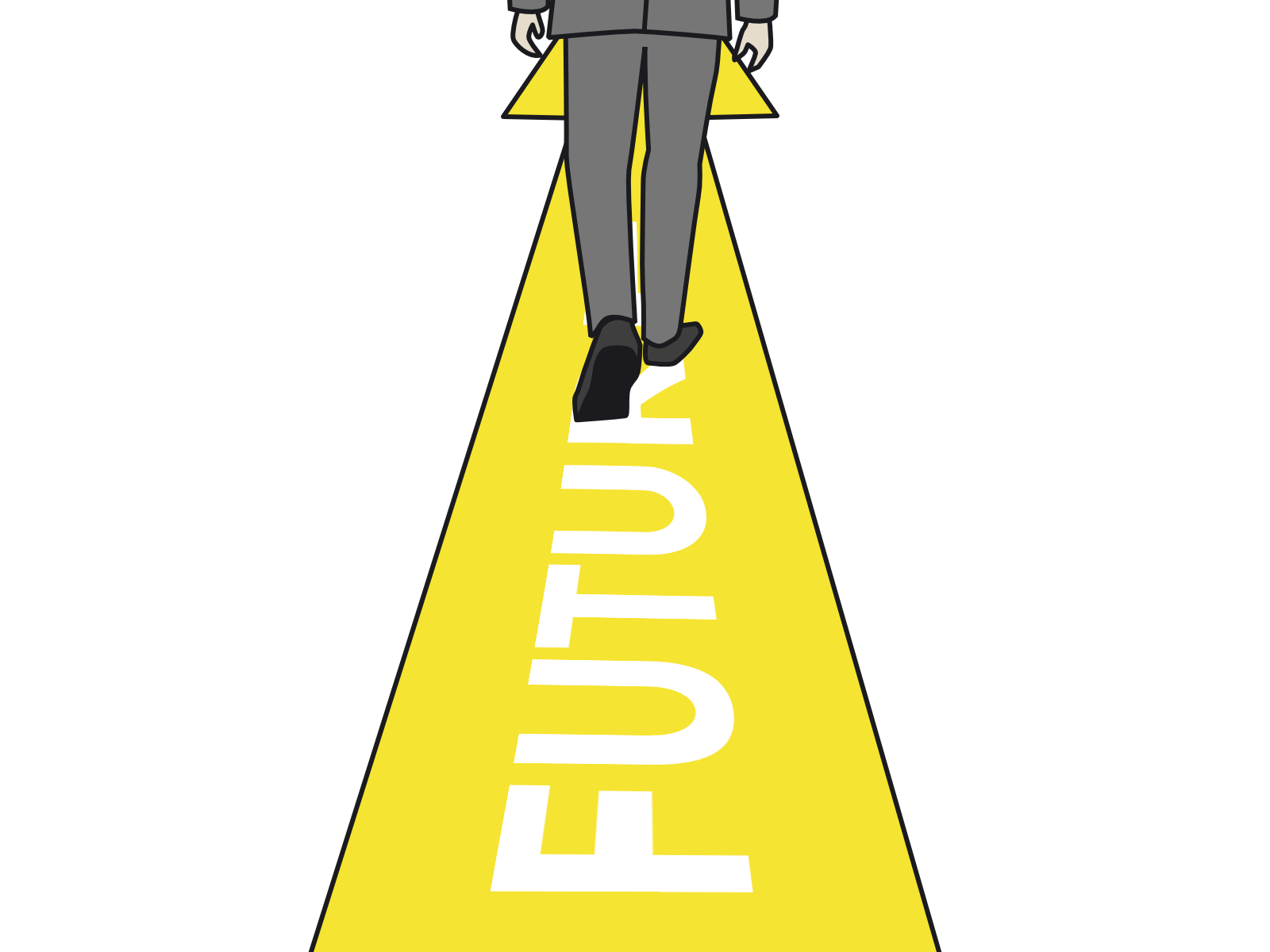
ここでは最初に、体系的廃棄の失敗事例として、ドラッカーが挙げている「自動車産業が昨日を守ることで明日を犠牲にした事例」を紹介します。
1.1990年代、GMの決断
-
1970~1980年代にかけて、米国市場において日本車メーカーが躍進したことはよく知られています。この間、日本車メーカーのシェアが大幅に上昇したのですが、その多くはトップ企業であるゼネラルモーターズ社(GM)から奪ったものでした。GMのシェアは50%から30%にまで低下し、GMは値下げと値引きといった対応策に終始したのです。
そこで、1990年代に入り、GMは新型車サターンを投入し反転攻勢に出ました。サターンは、日本車を意識して開発された車でした。設計、生産、マーケティング、アフターサービスに関して、日本車の延長にある車だったのです。
この車は、新しい米国車の登場を待ちわびていた米国市場に受け入れられて成功を収めました。しかし、サターンは日本車から市場を奪い返したわけではなかったのです。サターンは、GMの二つの事業部門、オールズモービルとビュイックの市場を奪い取っただけだったのです。つまり、サターンの投入によっても、GMの市場シェアは回復しなかったのです。
GMはこの事態を受けて間違った判断をしてしまいます。サターンの生産規模の拡大ではなく、オールズモービルとビュイックの工場の近代化のために、多額の投資を行ったのです。これは、成果を生まないまったく不毛な試みでした。サターンは失速し、オールズモービルとビュイックの事業部門も低迷したままでした。
GMは、まさに「昨日を守り、明日を犠牲にする」道を選んでしまったのです。
では、GMはどのようにしたらよかったのでしょうか。一つは、斜陽となったオールズモービルとビュイックの生産を中止・縮小すること、もう一つはサターンの成功を拡大するために、そこに経営資源を集中的に投入することです。GMは適切な体系的廃棄を行わなかったことで、経営基盤に大きなひびを入れてしまったのです。
2.出版社のチャレンジ
-
次に、実行方法の体系的廃棄の事例を紹介します。ドラッカーが調査した当時、出版業では売上の50~60%、また利益の大半を刊行後一年以上経過した既刊書に依存していました。
しかし、多くの出版社では、新刊書ばかりに気を取られてしまい、既刊書に目を向けることは少なかったのです。こうした状況下で、米国のある出版社が既刊書のマーケティングを重視する方針を打ち出しました。しかし、その出版社は十分な成果を挙げることができませんでした。方向性は正しかったのに成果が出なかったのです。
そこで、この出版社の一人の役員が、「もしも、これから出版社を立ち上げるとするならば、果たして、今のやり方で既刊書を売ろうとするだろうか?」という質問をしました。この質問に対して、経営陣の全員が「ノー」と答えたことで、既刊書の販売方法の見直しをすることになったのです。この出版社は、新刊書を扱う部門と既刊書を扱う部門を分離し、それぞれ独自の取り組みを行うようにし、その後、大きく業績を向上させることができました。
これが実行方法の体系的廃棄です。
こうした体系的廃棄は、事業のあらゆる局面で行われるべきものです。現在のようなグローバル化、情報化の発展したビジネス環境においては、ますます体系的廃棄のテーマが増えているといえるでしょう。
次回 その44「継続的改善の習慣化」
著者紹介
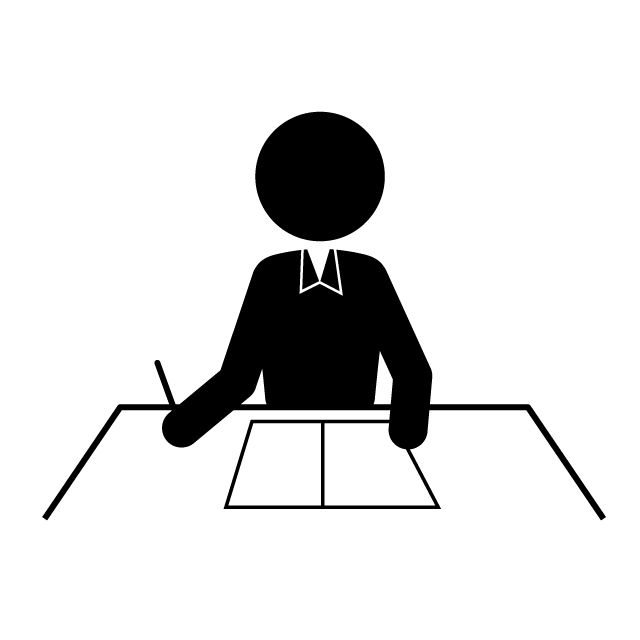 浅沼 宏和
浅沼 宏和
早稲田大学政治経済学部卒、中央大学大学院法学研究科卒、名古屋学院大学 論文博士
「社会制度変容の力学 -内部統制制度・リスクマネジメント・コーポレートガバナンス一体化の論理」
講座に関するご質問、その他通信教育に関するお問合せは、下記担当者までお願いいたします
2026年総合通信教育ガイドについて
ご請求は下記より受け付けております
「AIは、現場力でこそ生きる。」


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる