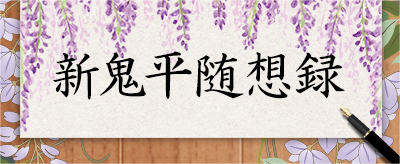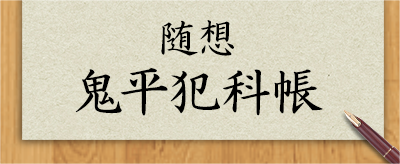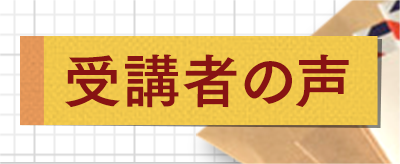メールマガジン
お金について、今一度学んでみませんか?/連載:ものづくり人のためのドラッカー[その42]

*2025年11月20日(木)
気がつけば日脚もめっきり短くなり、冬の訪れを感じております
皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日は、
- 『社会人のお金「基本のキ」』ご案内
- 「ものづくり人のためのドラッカー」その42
について、ご案内いたします。ぜひ最後までご拝読いただければ幸いです。
お金について、今一度学んでみませんか?

お金について考える良いきっかけに
年末調整の時期がやってまいりました。添付書類の準備や申告書の作成に苦慮することもあるかもしれませんが、お金に関する多くの情報に接する貴重な機会でもあります。自分自身や家族に関わるお金について考える良いきっかけにもなり、ライフプラン(人生設計)の見直しにつなげることもできます。ライフプランをまだ立てていない方も、この機会にぜひ考えてみてはいかがでしょうか。

ライフプランを考えるために
結婚・子育て・マイホームの取得など、長い人生に待ち構えるイベントは人によってさまざまですが、それぞれどれだけのお金がかかるのか把握する必要があります。
また、もしもの時の人生のリスク(思わぬ事故で働けなくなる等)についても、どのように備えていけばよいのか、考えておかねばなりません。そして高齢化社会の中、老後の年金制度はどのような仕組みになっているのか、安心して老後を過ごすためにも早いうちから理解を深めておくと安心です。
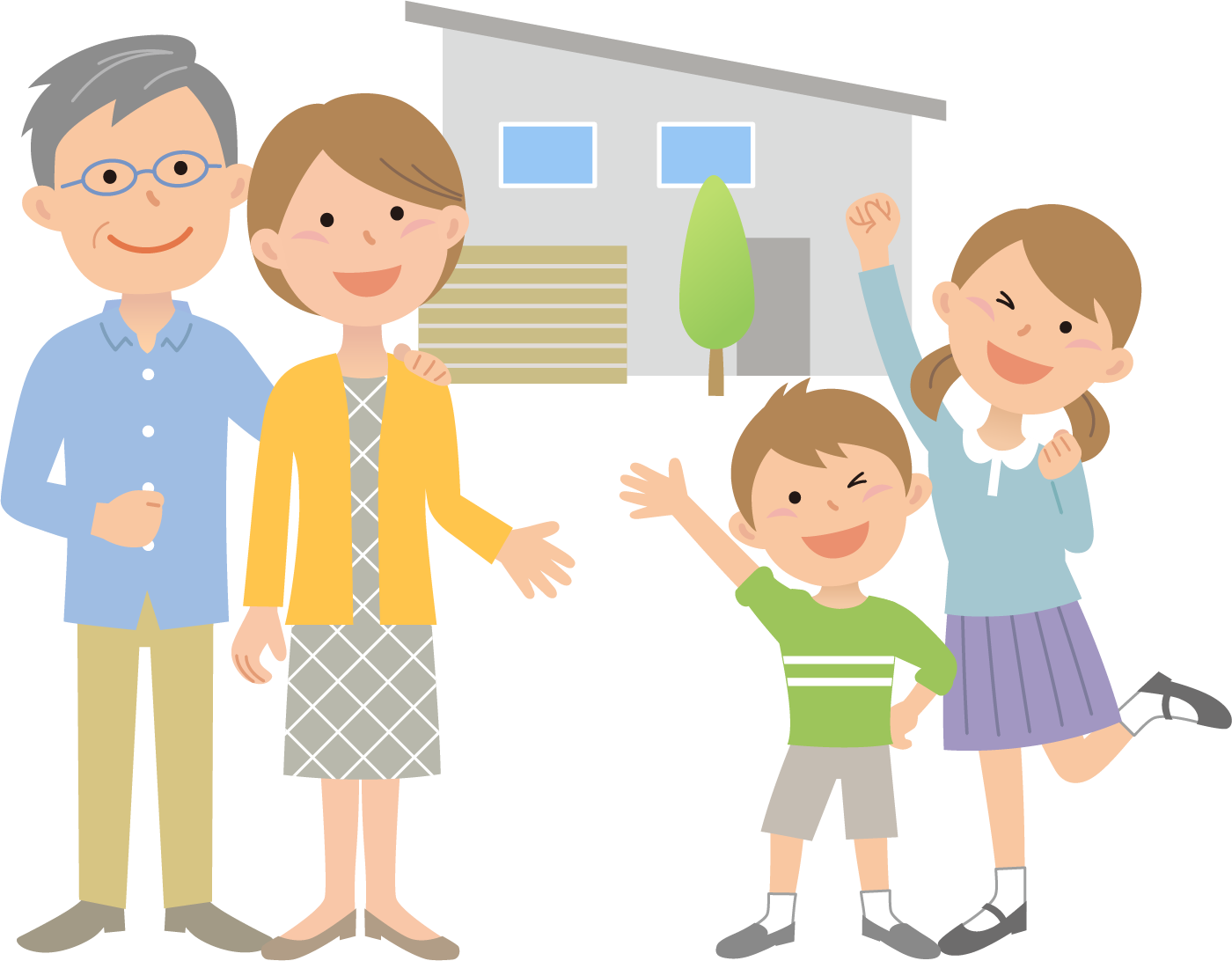
“人生にかかるお金”を学ぶことができます
JTEXの通信教育講座『社会人のお金「基本のキ」』は、毎年多くの方にご受講いただき、大変ご好評を頂戴しております。
ライフプランの設計だけでなく、給料明細の項目から資産運用や税金、相続など幅広くお金について学ぶことができる講座となっております。また、入社3年目の「誠君」と人事部で先輩の「愛さん」が登場し、事例を用いながらわかりやすく解説しているのが特長です。
本講座によりお金について学び、皆さまの人生設計の一助となれば幸いです。
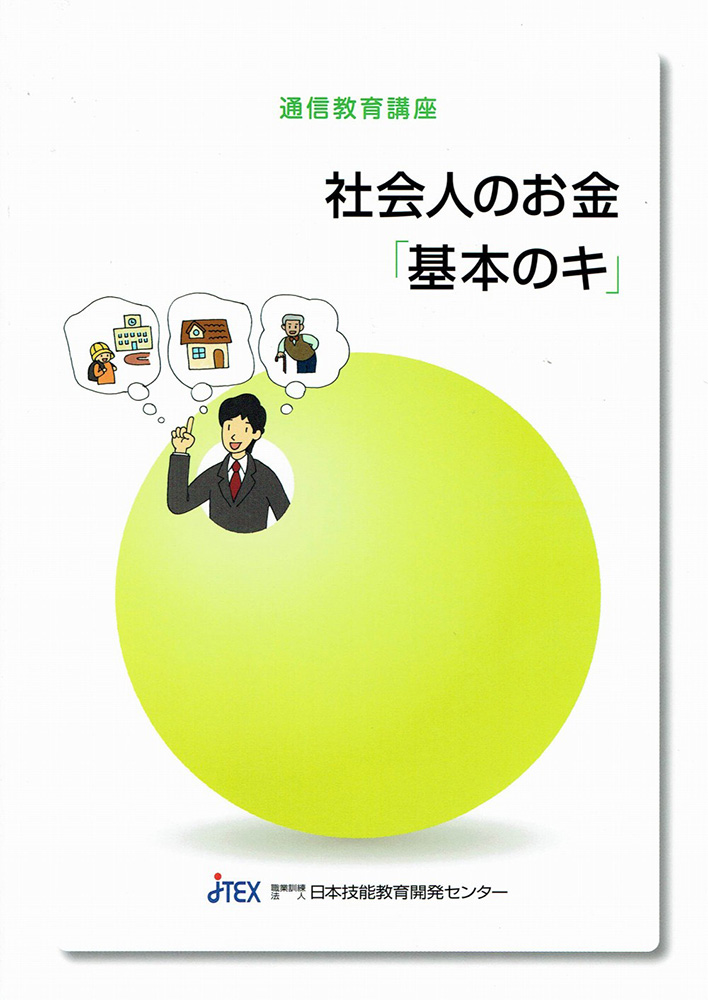
新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」
~イノベーションは天才のひらめきではなく、明日に向けた仕事である
著者 浅沼 宏和
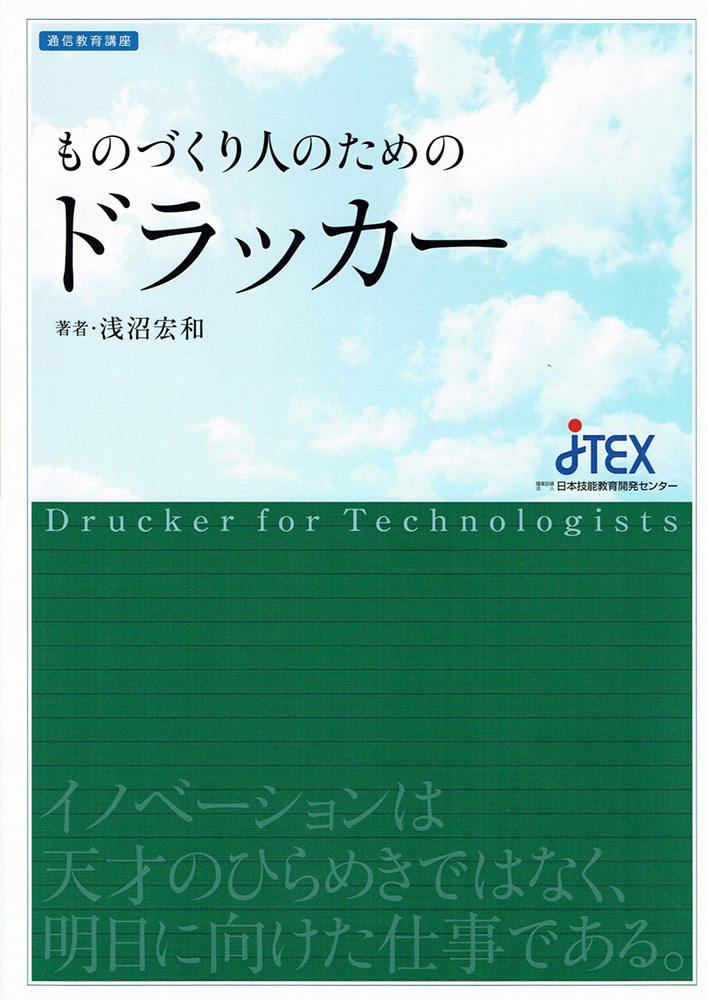
“ものづくり人“とは、ものづくりに関わる、経営者、技術者・技能者、営業・管理部門までのすべての人を、そう呼んでいます。
この連載はドラッカーの11冊の著書からリベラルアーツとしてのドラッカーをまとめたものです。
どこかに、役に立つ一言が含まれていることと思います。
ぜひ、ご愛読ください。
その42 体系的廃棄の仕組化
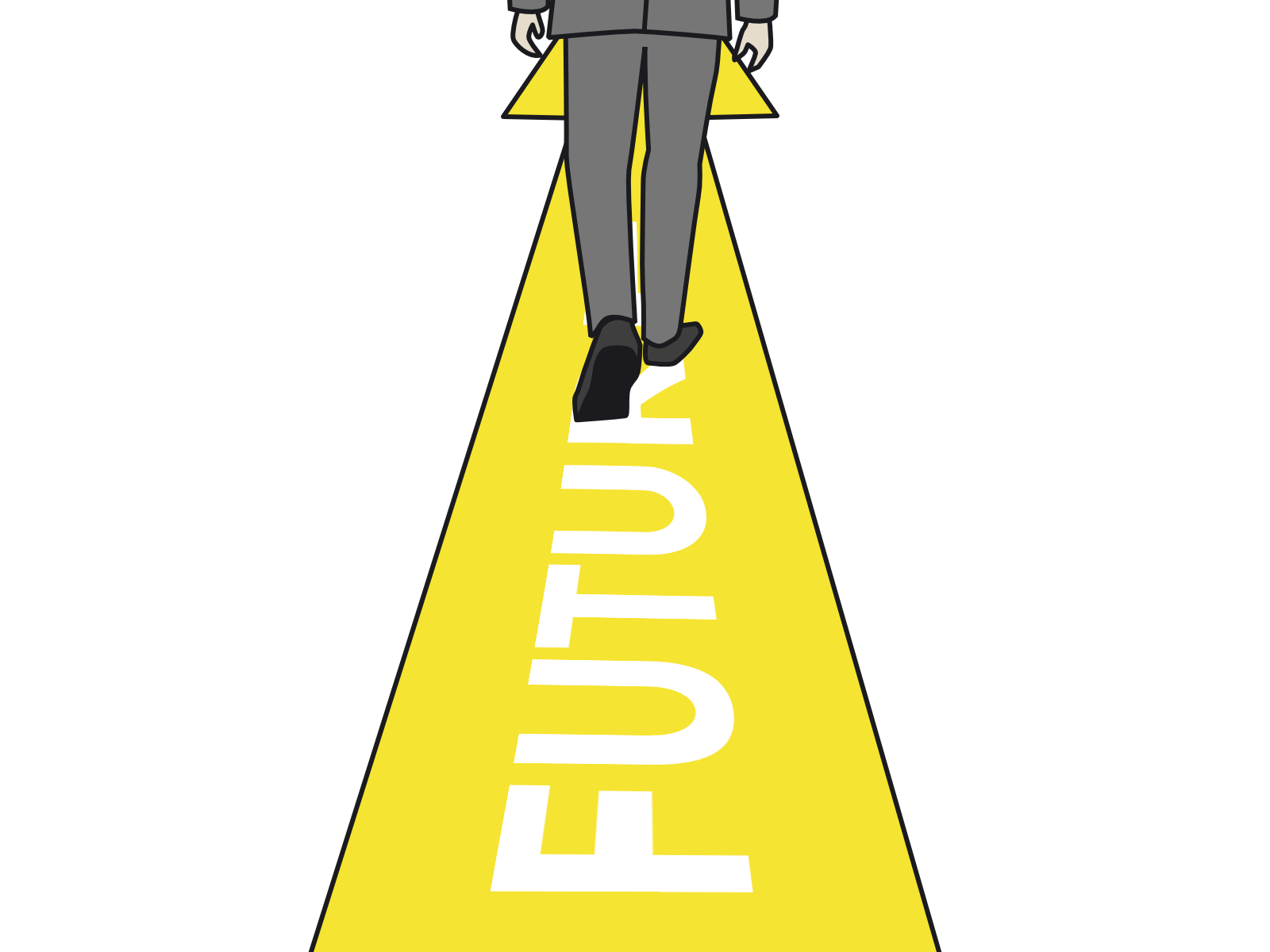
ドラッカーがチェンジ・リーダーを生み出すための仕組みで最も重視しているのは、体系的廃棄です。体系的廃棄こそが、変化を可能にするための第一条件なのです。
体系的廃棄とは、成果のあがらなくなった活動や取り組みを見つけ、それを廃棄することを仕組化することです。
体系的廃棄を行うと、資源に余裕が生まれます。「昨日を棄てることなくして、明日をつくることはできない」とドラッカーはいっているのです。昨日を守るために貴重な経営資源を投入することをやめて、新しいものを生み出すための資源を確保することが、体系的廃棄の目的です。
1.イノベーションのための体系的廃棄
-
イノベーションのための資源を確保するのに最も有効な方法が体系的廃棄なのです。優秀な人材を成果のあがらない過去の取り組みから解放することが、イノベーションには不可欠です。イノベーションには困難がつきものです。困難であるからこそ、最も優秀な人材を投入する必要があるのです。ドラッカーは「イノベーションには、実証済みの能力のある人材のリーダーシップを必要とする。」といっています。
体系的廃棄とは、あらゆる製品・サービス、業務プロセス、流通チャネル、顧客ニーズを見直すことです。しかもそれを思いついたときに行うのではなく、常時点検するのです。ドラッカーは、そのための基準として、次のような質問を用意しています。
「今、それを行っていなかったとしても、新たにそれを行おうとするか?」
この質問の答えが「ノー」であるならば、ただちにそれをやめなければならないのです。「もう少し様子を見てみよう」「まだまだ検討の余地があるはずだ」と考えて時間を浪費せず、ただちに変化を受け入れることが必要だといいます。
2.体系的廃棄の三つの状況
-
具体的には、
第一に、あらゆる製品・サービス、業務プロセス、顧客ニーズなどが “まだ数年ある”という状況においては、体系的廃棄が正しい行動である。
こうした場合、事業の寿命が思ったよりも短いことが多いうえに、過去を守るために多大な経営資源をつぎ込んでしまっています。非常にリスクの高い状況ですから、ただちに行動するべきなのです。
第二に、追加コストがかからないというだけの理由で、現在の製品・サービス、業務プロセス、市場などが維持されているのであれば、体系的廃棄を行うべきである。
たとえコストがかからなくても、何も生み出していないようなものは維持するべきではないのです。また、得てして、、それらにも見えないコストがかかっているものなのです。コストのかからない資産など存在しないのです。
第三に、成果をあげるべき製品・サービス、業務プロセス、市場などについて、既存の事業が邪魔をするようになった場合には体系的廃棄を行う。
いずれにしても、体系的廃棄には断固とした決意が必要になります。常に事業のあらゆる面を検討して、体系的廃棄を行っていく必要があるのです。
3.流通チャネルの体系的廃棄
-
また、ドラッカーは、体系的廃棄には現に行っていることをやめるだけでなく、実行の方法自体を廃棄する場合もあると述べています。実行の方法自体が陳腐化しているかどうかの見極めは、さらに難しくなりますが、この場合においても「今これを始めるとしたら、今の方法で行うか?」という基準に基づいて判断しなければならないといっています。
乱気流の時代にあっては、流通チャネルの変化の速度が速いため、従来のチャネルが陳腐化していないかに注意を払わないといけないのです。
次回 その43「昨日を守り、明日を犠牲にした事例」
著者紹介
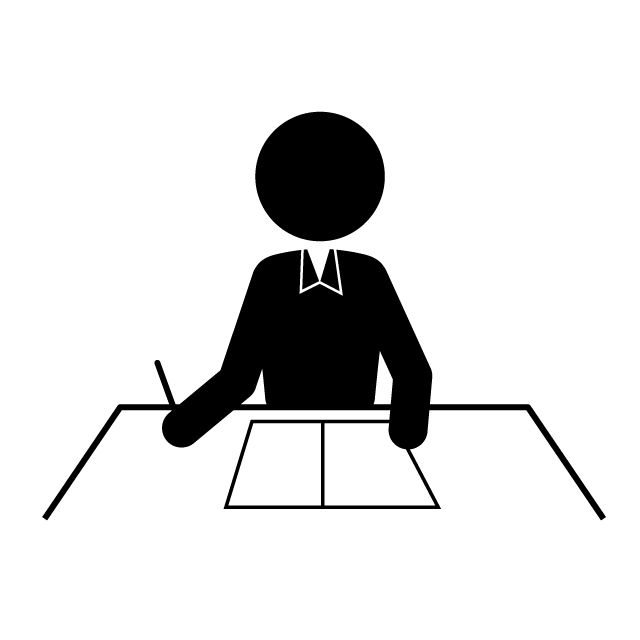 浅沼 宏和
浅沼 宏和
早稲田大学政治経済学部卒、中央大学大学院法学研究科卒、名古屋学院大学 論文博士
「社会制度変容の力学 -内部統制制度・リスクマネジメント・コーポレートガバナンス一体化の論理」
講座に関するご質問、その他通信教育に関するお問合せは、下記担当者までお願いいたします
2026年総合通信教育ガイドについて
ご請求は下記より受け付けております
「AIは、現場力でこそ生きる。」


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる