資格別コンテンツ
機械保全技能士とは|機械保全技能士を取得するメリットや業務内容、試験の概要を詳細解説!
機械保全技能士とは?
資格概要・取得するメリット・
取得後の業務内容等を解説!
機械保全技能士は機械保全技能検定に合格することで認定されます。技能検定は業務を行う上で必要な技能の習得レベルを評価するもので、130職種の試験が設けられています。そのなかでも受験者数が多く、人気資格の一つが「機械保全技能士」です。
機械保全技能士は製造業に従事する方や、製造業への転職を考えている方にとっては注目の資格ですが、具体的にはどのような資格なのでしょうか。本ページでは、機械保全技能士の資格について、取得するメリットや、主な業務の内容、試験概要などを詳しく解説すると共に、検定に対応したJTEX通信教育講座も紹介していきます。
目次
技能検定 認定訓練(学科試験免除)コースのご案内

JTEXでは各種修了条件をクリアいただくことにより、1・2級技能検定の学科試験が免除となる、下記認定訓練コースを全国の企業様にご紹介しており、延べ40,000名を超える方々が技能士として活躍しています。
認定訓練コース
(4月開講)1・2級技能士コース・電子機器組立て科(電子機器組立て作業)
(4月開講)1・2級技能士コース・機械加工科(普通旋盤作業/数値制御旋盤作業)
(9月開講)1・2級技能士コース・機械検査科(機械検査作業)
(10月開講)1・2級技能士コース・機械保全科(機械系保全作業/電気系保全作業)
認定訓練コースを活用することで、計画的に国家資格取得を目指すことができます。
ご受講を希望される方は、企業の教育ご担当者様にご相談の上、弊社までご連絡をお願いいたします。
連絡先 TEL:03-3235-8686 連絡先メール:jtexweb1@jtex.ac.jp
機械保全技能検定 試験日程

機械保全技能検定の職種(試験区分)は、「機械系保全作業」「電気系保全作業」「設備診断作業」の3つに分かれています。
また、各職種は「特級、1級、2級、3級」「学科試験、実技試験に分かれており、3級が学科、実技試験共に例年6、7月に実施され、それ以外の級は学科試験が12月~翌年1月に、実技試験が12月~翌年2月に実施されます。
詳しくは試験実施団体のホームページをご参照ください。
機械保全技能士とは
機械保全技能士についての説明を始める前に、「機械保全」という用語に付いて説明をしたいと思います。 「機械保全」とは、工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持保全するために行われる重要な仕事です。具体的には、機械設備のメンテナンス計画の作成や実施、劣化の予測や欠陥の発見、異常発生時の修理の対応のほか、生産設備のデータ収集や解析、判定などの情報管理等、各種製造現場で行われている共通的な作業です。 このような機械保全における技能の習得レベルをはかる機械保全技能検定は、工場やプラント等で機械や設備を扱う各種企業では必須の検定と言えるでしょう。
機械保全技能士が働く場所は、基本的に工場やプラントの製造現場です。製造現場には発電・配電、ガスや給排水、消防など、いろいろな種類の機械設備がありますが、これら機械設備のどこか一箇所に故障や不具合があると全体の稼働がストップし、製品の生産ができなくなったり、企業が一番避けたい労災事故が発生する確率が高まったりと、企業は大きな損失を被ってしまいます。そのような事態を防ぐために、機械保全技能士は、生産ライン全体の故障や不具合を日々の点検によって予防します。
このような業務を行うに当たって、機械保全技能士には機械保全に関する知識や技能の他にも、小さな異常にも気づく注意力やその場の状況に応じた対応力・判断力、各部署との連携を図るための調整力なども求められるのです。
機械保全技能士 取得のメリット

ここまで機械保全技能士について説明してきましたが、実際にこの資格を持っていなくても、資格保有者と同様の業務を行うことは可能です。しかし、機械保全技能士の資格を取得することで下記のようなメリットがあります。 通信教育等を活用して効率的な学習を進め、合格を勝ち取りましょう!
1.機械保全に関する幅広い知識やスキルを習得することができる。
機械保全技能士の資格取得に向けた勉強をすることで、機械や電気に関連する知識や、各設備に異常があった際の対処法などを幅広く学ぶことができます。資格取得者は学んだ知識を生かし、工場内での機械保全や設備に関するトラブル対応といった保全業務一般に携わることが可能になります。さらに、工場内で設備のメンテナンス計画をどのように進めるかの計画立案や、他部署や外部の設備関連会社との打ち合わせなどを任せられることもあるでしょう。
2.国家検定保有者としてキャリアアップにつながる。
機械保全技能士の資格取得をすることは、自身のキャリアアップにもつながります。企業によっては機械保全技能士の資格取得が「入社5年目に2級、入社10年目に1級」を取得することで昇格するといった、昇格要件に含まれていることもあります。
業務経験に応じた等級に合格することで、現場のリーダーとして活躍することも可能になるでしょう。また、資格手当が支給されるケースもあり、給与面でも優遇されることもある資格といえるでしょう。
3.転職する際に有利になる。
機械保全技能士取得のメリットの一つとして、転職時に有利であることが挙げられます。機械保全技能士は技能検定を受験して合格しないことには取得できず、また、全国で多くの方が受験している検定であることから、取得することにより、自身の能力を客観的に示すことができます。採用する企業側も、機械トラブルを防ぎ、生産性を高めることのできる人材を採用したいと考える点から、転職に際してのアピールになることは請け合いです。
各等級レベル(特級・1級・2級・3級)

機械保全技能士はレベルが高いものから順に、特級・1級・2級・3級と等級が分かれており、特級を除いて選択作業別に試験が実施されます。1級と2級は「機械系保全作業」「電気系保全作業」「設備診断作業」、3級は「機械系保全作業」「電気系保全作業」から選択することとなります。
各等級では求められる知識や技能が異なるのはもちろん、職場での階層や立場にも違いがあり、下記のように分類されます。
特級
企業内で機械保全に関わる業務の監督者として働く管理職の人を対象としており、保全分野における監督者の技術評価として役立てることが多いです。
1級
企業の保全部門などでリーダー的な役割を担う人を対象としています。保全部門でリーダーとして活躍するに当たっては、他のメンバーに助言したり、指導したりする場面が出てくるため、知識豊富な1級機械保全技能士資格取得者は適任と考えられます。
2級
生産現場で保全関連の知識を必要とする新入社員から若手、中堅レベルのオペレーターや保全部門の社員などが対象となります。機械保全に関する全般的な知識を習得します。
3級
3級は初級レベルの知識の習得が求められ、学生や新入社員などを対象としています。高校生や新入社員に対して、社内教育を実施した際の成果を確認するために利用されることもあります。
機械保全技能検定 試験概要
試験日程
試験は3級が例年6、7月に実施され、それ以外の級は12月~2月に実施されます。
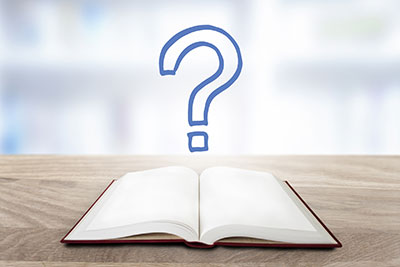
受検資格
機械保全技能検定の受検には、受検資格が設けられており、等級ごとに必要な機械保全に関連する実務経験の年数が異なります。3級は実務経験を問われず、どなたでも受検可能です。2級は2年以上、1級は7年以上の機械保全に関連する実務経験が必要です。特級は1級合格後5年以上の機械保全に関連する実務経験が必要になります。
また、1・2級の機械保全技能検定の受検資格は学歴等による短縮要件が設けられており、工業高校や大学・短大の工学部の卒業、職業訓練の修了などがこれに該当します。また、2級は3級の合格によって実務経験なしで、1級は2級合格後2年以上、3級合格後4年以上の実務経験によって、受検することが可能となります。
出題内容
いずれの等級も学科試験と実技試験が実施されます。等級が上がるほど、試験の難易度も高くなり、等級が下がるにつれ基礎的な問題を中心に出題されます。
学科試験
特級以外の試験は選択作業別に実施され、1級・2級は「機械系保全作業」「電気系保全作業」「設備診断作業」の3つから、3級は「機械系保全作業」「電気系保全作業」の2つから作業を選択します。
1級・2級・3級 共通科目
1級・2級・3級における学科試験の共通科目は、「機械一般」「電気一般」「機械保全法一般」「材料一般」「安全衛生」となり、多肢択一式の正誤問題で出題されます。
1級・2級・3級 選択科目
選択科目は試験申込時に選択した作業により、3級は「機械系保全法」と「電気系保全法」のいずれか、1級・2級は「設備診断法」を加えた3つの内の1つとなります。こちらも多肢択一式の正誤問題での出題です。
特級科目
特級の科目は「工程管理」「作業管理」「品質管理」「原価管理」「安全衛生管理及び環境の保全」「作業指導」「設備管理」「機械保全に関する現場技術」となり、多肢択一式の正誤問題で出題されます。
実技試験
1級・2級・3級
実技試験は、主に異常発生時の原因特定やその際の対応に関する問題が出題されます。機械系保全作業と設備診断作業は、資料などを見て判断するマークシート方式の解答です。電気系保全作業は、実際作業として回路組立を行う出題です。
特級
実技試験は、現場における課題を表や図表、グラフなどを用いて提示し、工程管理・作業管理などに関する計画立案の技能を測る問題が出題されます。
JTEX 機械保全技能検定対策 通信教育講座が選ばれる5つの理由

JTEXでは、技能検定試験の受検対策に役立つ通信教育「技能検定対策受検準備講座」を随時開講しております。(注)年1回10月開講限定の認定職業訓練(学科試験免除コース)とは異なります。
各科目の「技能検定に係る技能検定試験の試験科目及びその範囲」に準じ、その項目を忠実に網羅するものであり、体系的にわかりやすく学習できる構成となっております。JTEX通信教育講座の受講を通じ、機械保全に関する幅広いトータルな知識を身に付けて、技能検定合格を目指しましょう!
JTEX 機械保全技能検定対策 通信教育講座ラインナップ

特級技能検定の基準細目に沿って編集したオリジナル通信教育テキストで学ぶ『特級技能検定受検準備講座(共通科目)』や、生産設備保全の中核となる人材を目指すために、1・2級技能検定の基準細目に沿って編集したテキストで学ぶ『技能検定1・2級 わかりやすい「機械保全」(機械系/電気系)【選択制】』、過去の試験問題に取り上げられた内容に焦点を当てた通信教育教材で、3級機械保全技能検定試験合格を目指す『技能検定3級「機械保全」(機械系保全作業)』、それ以外にも実技試験対策としてセミナーの開催等、多種にわたってご紹介可能です。
ご自身の学びたい内容に合わせた講座を選択して、合格を目指しましょう!








