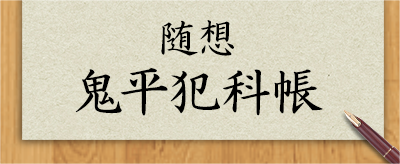新鬼平随想録
第46回「本門寺暮雪」
今回は池波の自選作の第4話「本門寺暮雪」(文春文庫9巻)を取り上げ、その概要と感想を述べてみたい。
正月の20日の朝。朝餉を済ませた平蔵は、市中が平穏無事、天気も上々なので、妻・久栄に細井彦右衛門殿の見舞いに出かけたいといった。細井は小普請組にいて、まだ無役の6百石の旗本であるが、最近労咳に取り付かれてしまった。細井の亡父・光重に若い頃助けられた平蔵は、薬を届けたりして細井を救いたいと思っている。そんな気持をよく知る久栄は、夫の外出の支度を整えるため、居間から廊下へ出た途端、べっ甲の笄(女性がまげに挿して飾りとする具)が廊下に落ち、2つに割れてしまった。不吉な予感がして、久栄はしばし立ちすくんだが、笄を拾って居間へ戻り、平蔵に今日の外出をやめる様に懇願する。しかし平蔵は、これがお上の御用なら、何といたす、久栄、俺に万一のことがあっても覚悟の上ではないか、男には男のなすべきことが日々ある、というと久栄を抱き締め、耳元で、安心いたせ、支度をしてくれとささやいた。
やがて平蔵は1人騎乗して清水門の役宅を出発した。途中芝・新銭座の表御番医・井上立泉方へ立ち寄り、薬を求める予定であったが、木村同心が表門に偶然いたので、彼に薬を求め芝・二本榎の細井屋敷に届ける様に命じ、二本榎へ直行する。赤坂、増上寺、赤羽橋を過ぎ、三田の通りから聖坂を登り切った時である。左手の済海寺の門前に乞食坊主がいた。井関録之助である。彼は平蔵と高杉道場の同門であったが、御家人の父の失態により家名が断絶し、永らく行方不明であった。それが数年前乞食坊主姿で江戸に現われ、ある事件で一役買ってくれたので、平蔵も密偵の様に使い始めたが、ここ1年位また行方不明となっていたのである。馬を寄せた平蔵が何を見ているのかと聞くと、井関は「凄い奴」と答えるので馬から下りてどの男だと聞くと、井関は向いの実相寺の茶店へ入った塗笠の浪人で、とても悪い奴だと答えた。平蔵は井関に1両を与え、後をつけてみろ、二本榎の細井屋敷で待つといって馬に乗り、その茶店の前を通りつつ中の塗笠の男の姿を一瞬見ると、ただものではないと直感した。
午後2時頃、平蔵は二本榎の細井家へ到着した。今日の細井彦右衛門は、去年11月に見舞った時より血色がよく、床の上に起き上がり、嬉しげに平蔵を迎えた。今夜は泊めてもらうつもりでと平蔵がいうと、尚更に夫妻が喜んだ。もともと両家は父親同志の親交が深かった。平蔵も少年の頃から細井光重によくなつき、義母の波津との不和に堪えかね、家を飛び出した時も二本榎へよく訪れたものである。細井光重は嫌な顔一つせず迎え、意見することもなく、2、3日泊って帰る時は小づかいを必ずくれた。今の平蔵が細井一家を何かと助けるのも過去の恩義を忘れないからである。細井家も後継ぎの幸太郎がまだ4歳であり、平蔵を頼りにしている。そんな平蔵が明日は池上の本門寺へ参詣いたそうと思いますといい、細井が今少し丈夫になれば御同道つかまつるのにと応じた時に、木村同心が薬を持って到着した。
他方井関が後をつけると、凄い奴は茶店を出て聖坂を下がり、三田4丁目、三田寺町を通り、三ノ橋を渡り、麻布へ入った。そして麻布一本松の長善寺の門前にある茶店「ふじ岡」へ入っていった。井関はその真向いにある増上寺・隠居所の中の木陰に腰をおろし、足を投げ出し、茶店を注視する。8年前に凄い奴に背中から腰にかけて切られたことを思い出す。どれ程待ったろう。「ふじ岡」が店先を掃き清めたりして店仕舞の支度を始めた。たまりかねた井関が箒を持つ女に尋ねると、塗笠の方は裏口から出ていったとの返事。しまった、感づかれていたか、今度は俺が後をつけられると思った井関が、不安にかられながら細井家へ駆け込んだ時は夕闇も濃くなっていた。人通りの絶えた二本榎の道へ、やがて凄い奴が現われ、細井邸の真向いにある国昌寺の門の下に腰をおろし、その夜から朝方まで、同じ姿勢のまま動かなかった。
一方細井邸の客間では、井関がその凄い奴のことを平蔵に語り始めた。家名断絶の後、井関は母方の遠縁のいる大坂で小さな町道場を開いたが、荒稽古なので門人が集まらない。空腹に水ばかり流し込んでいた井関のところへ葛籠師の紋造という男が訪ねてきて、30両で先生の腕前を買いたいというお人がいるという。このままでは餓死するので、その人に会うと、それは大阪の盛り場を支配する香具師の名幡の利兵衛であった。名幡は半金15両を出し、さる御家中のお侍を殺してほしい、3日後に手引きをするという。しかし翌朝になり、これはいけないと思い紋蔵にお金を返したが、その紋蔵がすぐに自殺したことを2ヶ月後に知った。すぐ江戸へ帰ろうと思い、桜宮の道場主・太田某に挨拶にいったが、桜堤で凄い奴に背から腰にかけて切り裂かれ、そのまま淀川へ落ちた。幸い船頭が助けてくれ、傷が直らないうちに伏見に送ってもらい、江戸へ帰ったのであった。それから8年。凄い奴は別の目的で江戸へきて、尾行する者が殺した筈の井関と気付いたに違いない。
午前9時。細井家の潜門を乞食坊主の井関が出た。閉じられた潜門の隙間から平蔵が外を見守ると、国昌寺の門から凄い奴が出てきて、井関の方向へ歩んでいく。平蔵も潜門を出た。井関は平蔵の書いた地図の道順通り、羕教寺門前を左に折れた筈であるが、凄い奴もそうする。平蔵はその跡を追わず、その先の相福寺の横道を左に折れ、東海道に出る下り坂の途中の常江寺の中に潜み、井関を待った。何かあったら常江寺まで逃げてこいといったが、井関は通り過ぎ、後から凄い奴もこない。たまりかねて平蔵は井関を追って法蔵寺までくると、井関がいて、凄い奴が途中で消えたという。それから2人は前後して高輪、品川、大森へと進むが、凄い奴は姿を見せず、ここで凄い奴の出現は半ばないとみた2人は、1里先の本門寺へ行くこととした。
池上村の本門寺は日蓮上人終焉の古蹟で、法華宗本化一宗正統の霊場である。平蔵と井関は総門傍のわらぶき屋根の茶店・弥惣に入った。雪がはらはらと降り始める。平蔵は弥惣の主人に今夜は泊めてもらおうといい、心づけをはずみ、井関と共に草鞋を草履にはきかえた。そして2人は熱いお茶で草餅を食べる。茶色の柴犬がしきりに平蔵に身を寄せてくるので、煎餅を買い、これを割って食べさせた。もう午後4時に近いので、2人は番傘をさし、96段もある急な石段を登り始めた。柴犬が尾を振りながらついてくる。平蔵が後5、6段で石段を昇り切るその時であった。
石段の上にふわりと人影がさし、先頭の井関がその気配で番傘をあげて見ると、横なぐりの刃風を受け、番傘を掴んだまま石段を転げ落ち、気絶した。凄い奴だ。それが石段を走り下り、腰を落して掬い上げる一刀を送るが、平蔵はとっさにさした番傘で身を守る。間髪入れぬ二の太刀も石段2段を飛び上り、辛うじてかわしたが、刀を抜く間もなく、三の太刀が足をなぎ払う。平蔵は飛び上って体当りをするが、凄い奴は驚いて飛び違う。石段に落ちると平蔵はすぐ片膝を立てて向き直り、ようやく小刀を抜く。しかし凄い奴が大刀を振りかぶると、平蔵はこれが最後かと感じた。この時初めて凄い奴の顔を見た。眉が薄く、唇の白い、気味が悪い程白い顔に、両眼だけが針の様に光っている。かなわぬまでも闘おうと覚悟を決めた平蔵に、自信に満ちた一刀を打ち込もうとした凄い奴が突然よろめいた。あの柴犬が凄い奴の右足に噛みついたのである。
あわてた凄い奴に猛然と平蔵が体当りをした。凄い奴は石段を落ちて、横倒しになり、すぐ跳ね起きたが、大刀が手から離れてしまい、すぐ石段を駆け下って逃げる。形勢が逆転し、粟田口国綱の大刀を抜いた平蔵が追い迫り、逃げ切れぬと悟った凄い奴が総門で立ち止り、振り向き様に脇差で切りつけたが、平蔵は国綱で払いのけ、一合、二合と打ち合った後脇差を叩き落とし、凄い奴の胴を払った。平蔵は国綱をぬぐって鞘に収め、石段を登り、井関に活を入れた。柴犬が平蔵に飛びついて、しきりに鼻を鳴らす。柴犬をしっかりと抱き締めると、平蔵は、両眼から涙を流しながら、これ、わしの子になるか、江戸へ一緒に行こう、茶店の親父から貰い受けるぞといった。雪は霏霏として降り続いている。
以上が概要であるが、以下感想を述べると、この小説では、平蔵が二本榎の細井家を訪ねるため、芝、三田、二本榎、高輪辺りの町名や寺名が沢山出てくる。これらは江戸時代に出版された「江戸切絵図」から引用されたものであるが、池波がこの様な引用をしたのは、小説の中で江戸の町を忠実に再現したかったからではないかと思う。それから二本榎という町名は昭和42年になくなったが、大変古い名前である。小説に出ている羕教寺の道をはさんだ反対側に、小説には出てないが、日蓮宗の上行寺(俳人・其角の菩提寺)があった。その門の左右には塚があり、大きな榎があったので、古くからその辺りは二本榎と呼ばれたという。明治に入っても町名として残ったが、昭和37年には上行寺が伊勢原市に移転し、42年には町名はなくなり、高輪1~3丁目になってしまった。
次に昭和23年の夏、池波は作家・長谷川伸の二本榎の邸宅を訪ね、入門を許された。前年に池波の戯曲が読売の演劇文化賞の佳作に入選したが、長谷川はその時の選者の1人であった。二本榎で万巻の書を借り、師に沢山の質問をして書いた戯曲が上演される様になると、小説を書く様にいわれたが、どうしても書けない。二本榎に伺うと、病中の師が起き上がり、これは書けない時の歌だといって「観世音菩薩が一体ほしいと思う五月雨ばかりの昨日今日」という歌を示してくれたという。池波はこの様な師の寛容さを思い出しながら細井光重の寛容さを書いたのではないかと思う(参考池波正太郎「私の仕事」朝日文芸文庫)。
最後に池波の師・長谷川伸は昭和38年6月に亡くなった。そのお通夜の日、2匹の愛犬が書庫の外壁のところに並んで、哀しげに泣き続けたそうである。その2匹の内の1匹が生んだ仔犬を貰って「クマ」と名付け、池波が飼った。池波の母は特に可愛がり、クマが重病になった時は、自室に入れた程だったが、昭和43年に死んだ(池波正太郎「ル・パスタン」文春文庫)。それから4年後の昭和47年にこの小説が書かれた。平蔵が柴犬を抱いて感謝する場面は実に感動的である。これで終わりかと思えば、次の小説「浅草・鳥越橋」で平蔵はこの犬にクマと命名して役宅で可愛がり、その後の小説「狐雨」、「犬神の権三」、「蛙の長助」でも平蔵がクマを可愛がる様子が描かれている。


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる