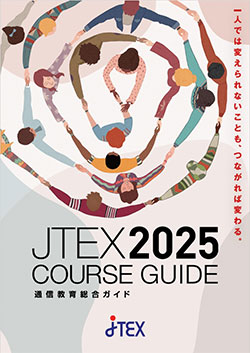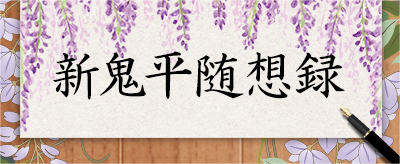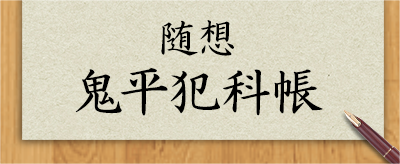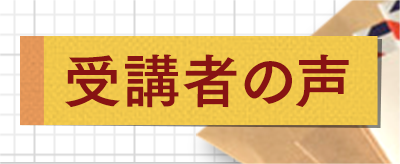メールマガジン
無料!「メンターの基本オンラインセミナー」開催のお知らせ! /連載:ものづくり人のためのドラッカー[その34]
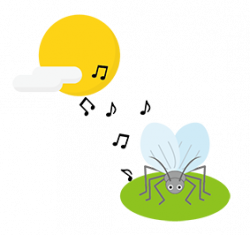
*2025年9月25日(木)
本日は、
- 無料Zoomオンラインセミナー開催のお知らせ
- 「ものづくり人のためのドラッカー」その34
について、ご案内いたします。ぜひ最後までご拝読いただければ幸いです。
2026年1月開講新講座 【新人・若手社員によりそう メンターの基本】
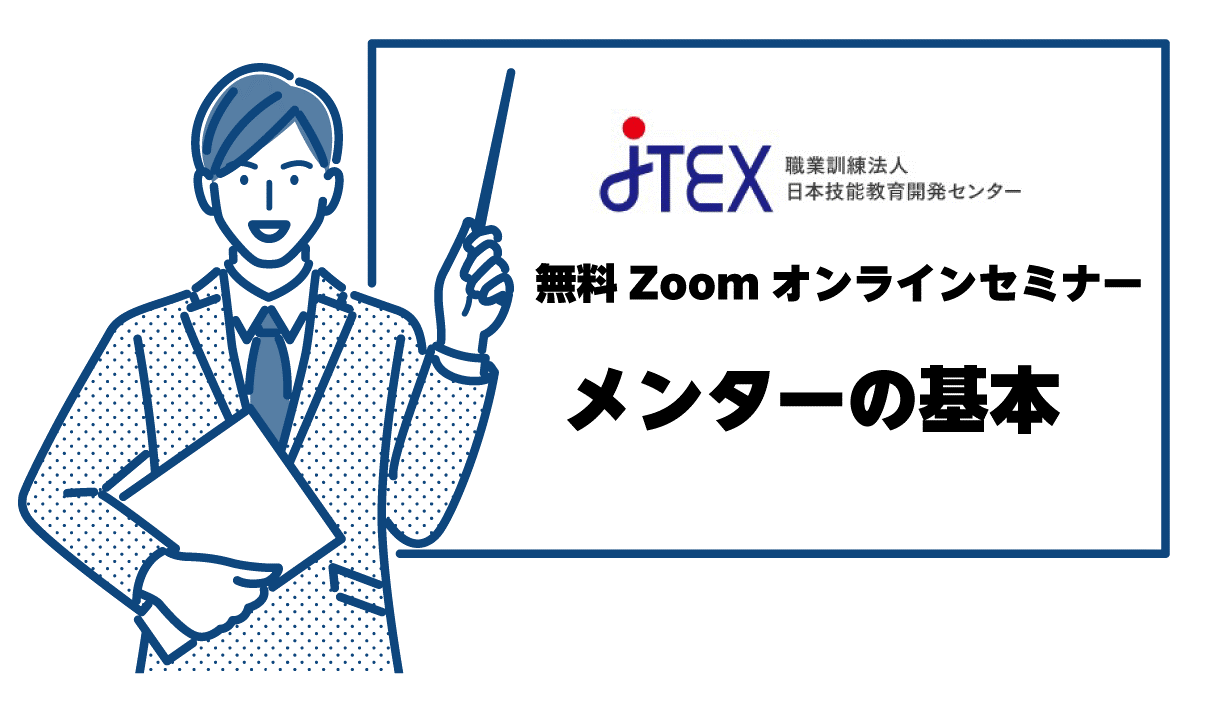
下記スケジュールにて無料オンラインセミナーを開催させていただきます。
- 開催予定日:11月12日(水)
- 開催時間 :13:00~14:00
※【本講座概要解説40分前後、その後質疑応答含】
初めてメンターとなる方が安心して取り組めるように

-
メンター制度とは、先輩社員が後輩社員の不安や悩みを聞き、サポートする社内制度のことです。今般、採用活動の難航や採用しても短期での離職が増加するなど、新人・若手社員の定着において、メンター制度の重要性は増しています。
今回は、新入社員や後輩のよき相談相手となるべく、メンターとしての役割や心構えを認識し、必要なコミュニケーションスキルを習得するきっかけにしていただければと思います。
通信教育開講記念として、皆様の貴重なお時間をいただき、私どもより今後の社内教育に少しでもお役立ていただけるような内容をお届けできればと考えております。

お申込み方法
- A:「参加希望」と記載いただきご返信の程お願いいたします。
閲覧用URLをメールにてお送りいたします。 - B:お電話でのお申し込みは、03-3235-8686までご連絡ください。
担当者より、閲覧用URLをお伝えいたします。
登壇講師・執筆講師
-
大伴 凌平(おおとも りょうへい)
株式会社東レ経営研究所 人材開発部 コンサルタント
新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」
~イノベーションは天才のひらめきではなく、明日に向けた仕事である
著者 浅沼 宏和
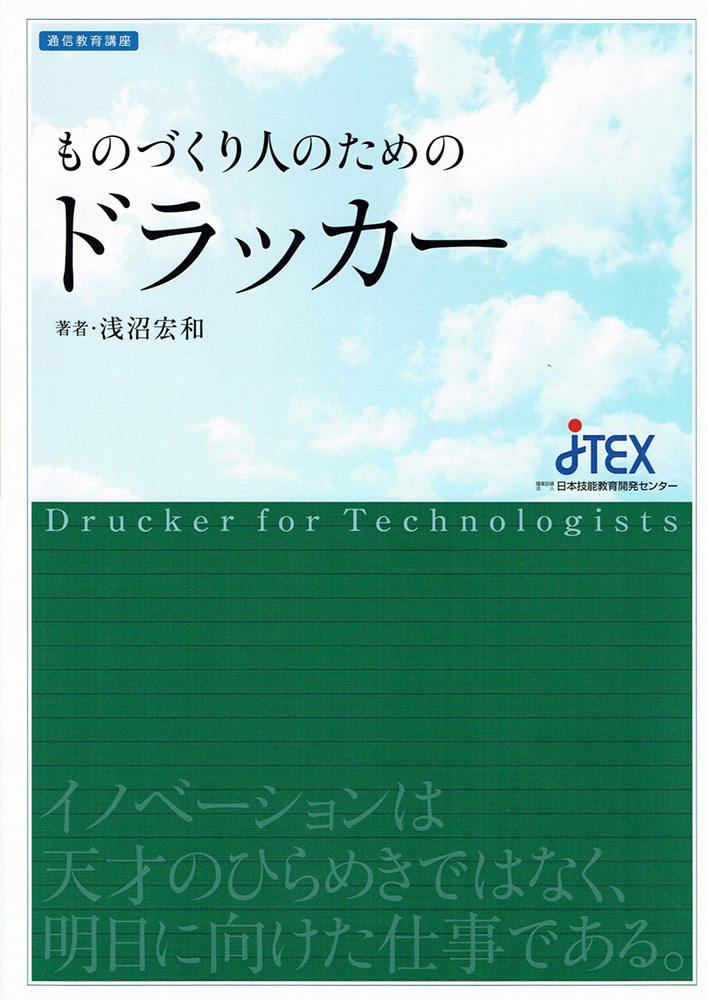
“ものづくり人“とは、ものづくりに関わる、経営者、技術者・技能者、営業・管理部門までのすべての人を、そう呼んでいます。
この連載はドラッカーの11冊の著書からリベラルアーツとしてのドラッカーをまとめたものです。
どこかに、役に立つ一言が含まれていることと思います。
ぜひ、ご愛読ください。
その34 イノベーションの必要性
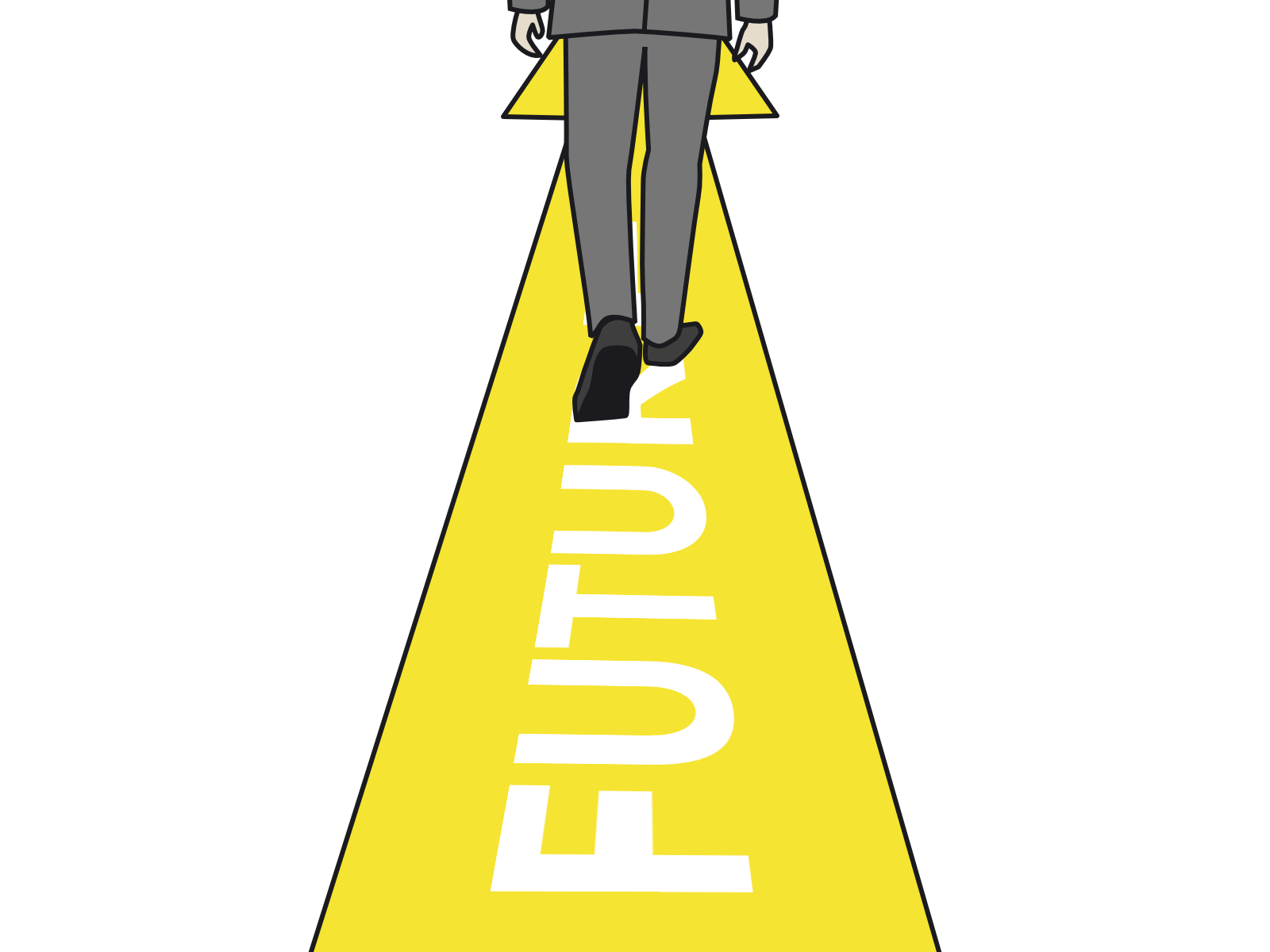
イノベーションは、企業にとって常に重要なテーマですが、特にイノベーションの必要性が高まるタイミングがあります。市場のニーズに対して、企業の提供する価値が割に合っていないときは、イノベーションのタイミングなのです。このようなタイミングに適切な価値提供を考えることができれば、事業を大きく発展させることができます。
1.大きな需要
-
需要が増大しているにもかかわらず、利益があがらないときがあります。ドラッカーは、第二次大戦後の鉄鋼業と製紙業がまさにそうしたタイミングにあり、明らかにニーズがあるのに、利益のあがるビジネスになっていなかったと指摘しています。
どちらも巨大な工程と設備を必要とする産業であり、それだけに工程の小さな変化が大きな収益性をもたらすはずなのです。この当時に、それらの産業にはイノベーションの必要性が生じていたのです。
需要が存在しているのに業績が伴っていない産業では、工程上、技術上、経済上の欠陥、もしくはそれらのいくつかが同時に問題となっている可能性が高いのです。
2.画期的技術
-
反対に、画期的技術であるにもかかわらず、何らかの理由で業績につながらない場合には、市場自体に制約や欠陥が存在している可能性があります。これは技術から市場を考えるという逆の視点といえます。
3.未来の業界
-
技術の予期について、さらに大切なのは、「業界で恐れられている事態は何か」、「今は起きるはずがないが、もし起きれば大変なことになることは何か」、「すでに顧客の役に立たなくなっているものは何か」といったことについて真剣に考えることです。
こうした質問は、自己否定につながる面もあるため、なかなか取り組みにくいものです。しかし、これらは自社の事業の存続を左右しかねない問題です。自社の立場で物事を考えてばかりいると、なかなか前に進めないものなのです。
技術のマネジメントとは、適切な問題意識に基づいて、何をするべきかを具体的に考えることです。必ずしも新技術が求められているわけではなく、新しい市場やチャネルを開拓することで済んでしまう場合もあります。しかし、こうした適切な問題意識がなければ、機会を逃すどころか、せっかくのチャンスを脅威と勘違いして、みすみす見逃してしまうかもしれないのです。
イノベーションの必要性は、技術を予期することからも明らかになります。技術を予期し、何が必要であり、何が可能であるのか、何が生産的であるのかを明らかにするためには、技術動向を理解する必要があります。
また、勘違いしやすいところですが、技術を科学と同一視してしまってもいけません。技術が発明そのものではなかったように、技術は科学そのものではありません。
ドラッカーによると、「技術とは科学に限らずあらゆる種類の新知識の応用から始まるもので、基礎的な科学の研究と科学の応用は違うということ」をきちんと理解しておく必要があります。
イノベーションのテーマは、技術の具体的なマネジメントの中で明らかになるものです。決して漠然とした考えからは生まれないのです。イノベーションとは、目的意識に基づくとても具体的な仕事なのです。
次回 その35「技術の変化とイノベーション」
著者紹介
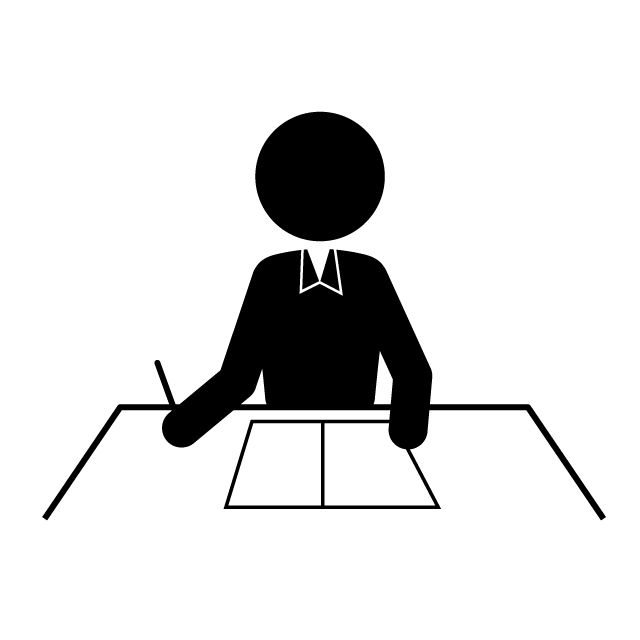 浅沼 宏和
浅沼 宏和
早稲田大学政治経済学部卒、中央大学大学院法学研究科卒、名古屋学院大学 論文博士
「社会制度変容の力学 -内部統制制度・リスクマネジメント・コーポレートガバナンス一体化の論理」
講座に関するご質問、その他通信教育に関するお問合せは、下記担当者までお願いいたします
2025年総合通信教育ガイドについて
ご請求は下記より受け付けております
「一人では変えられないことも、つながれば変わる。」


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる