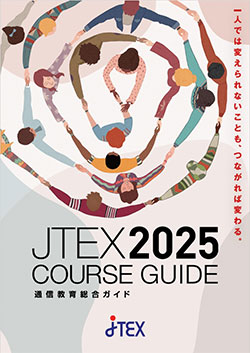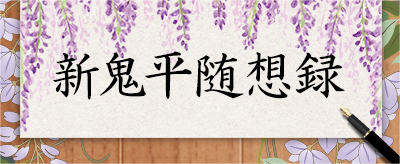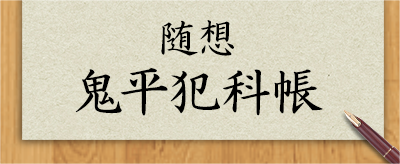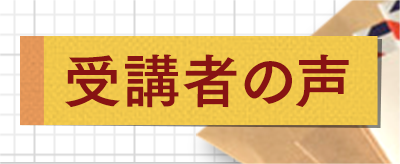メールマガジン
認定訓練コース機械保全科申込み※締切間近※ /連載:ものづくり人のためのドラッカー[その30]

*2025年9月4日(木)
朝の風に秋の気配を感じる頃となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日は、
- 認定訓練コース機械保全科申込み※締切間近※
- 「ものづくり人のためのドラッカー」その30
について、ご案内いたします。ぜひ最後までご拝読いただければ幸いです。
締め切り間近!
認定訓練コース【機械保全科】のお申込締切日が徐々に迫ってきております。
受講をご希望の方は早めのご対応お願い致します!
すでにお申込みを頂いておりますお客様におかれましては誠にありがとうございます!!
本年度も弊社が実施する認定訓練コース機械保全科のお申込みが徐々に到着してきております。
国家技能検定の学科試験が免除になるこちらのコースについては、毎年1回10月開講のみ受付となっております。
ご受講を希望されていて、まだお受付をしていない方におかれましては、早めの申込をお願い致します。
機械保全科 機械系保全作業 職業訓練短期課程 1級技能士コース
機械保全科 電気系保全作業
職業訓練短期課程 2級技能士コース
機械保全科 機械系保全作業 職業訓練短期課程 2級技能士コース
機械保全科 電気系保全作業

新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」
~イノベーションは天才のひらめきではなく、明日に向けた仕事である
著者 浅沼 宏和
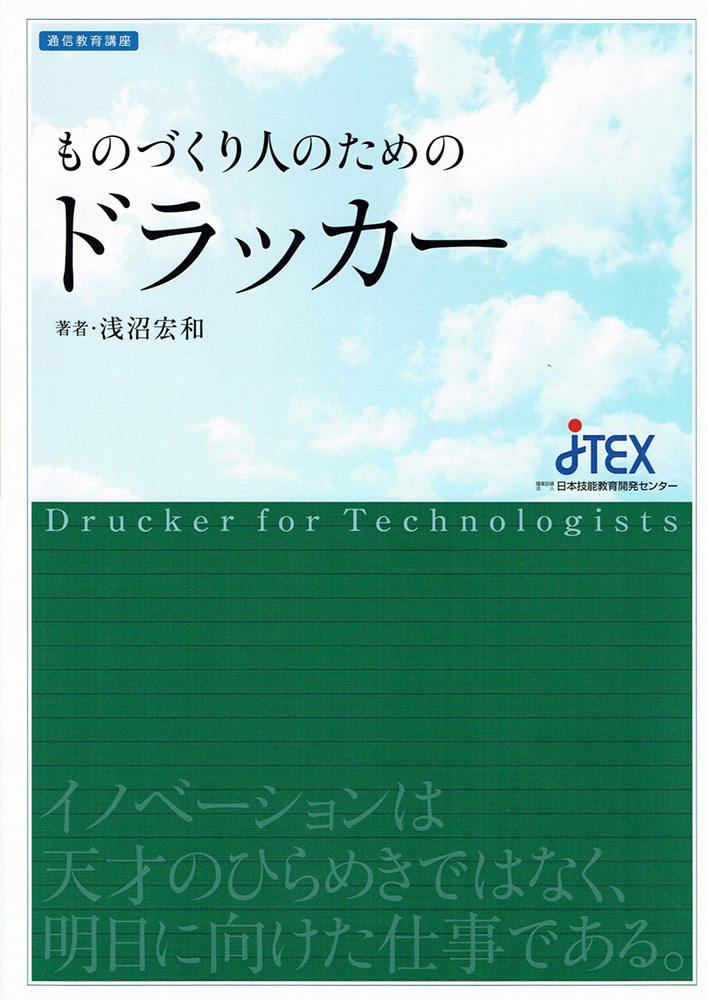
“ものづくり人“とは、ものづくりに関わる、経営者、技術者・技能者、営業・管理部門までのすべての人を、そう呼んでいます。
この連載はドラッカーの11冊の著書からリベラルアーツとしてのドラッカーをまとめたものです。
どこかに、役に立つ一言が含まれていることと思います。
ぜひ、ご愛読ください。
その30 イノベーションのための組織
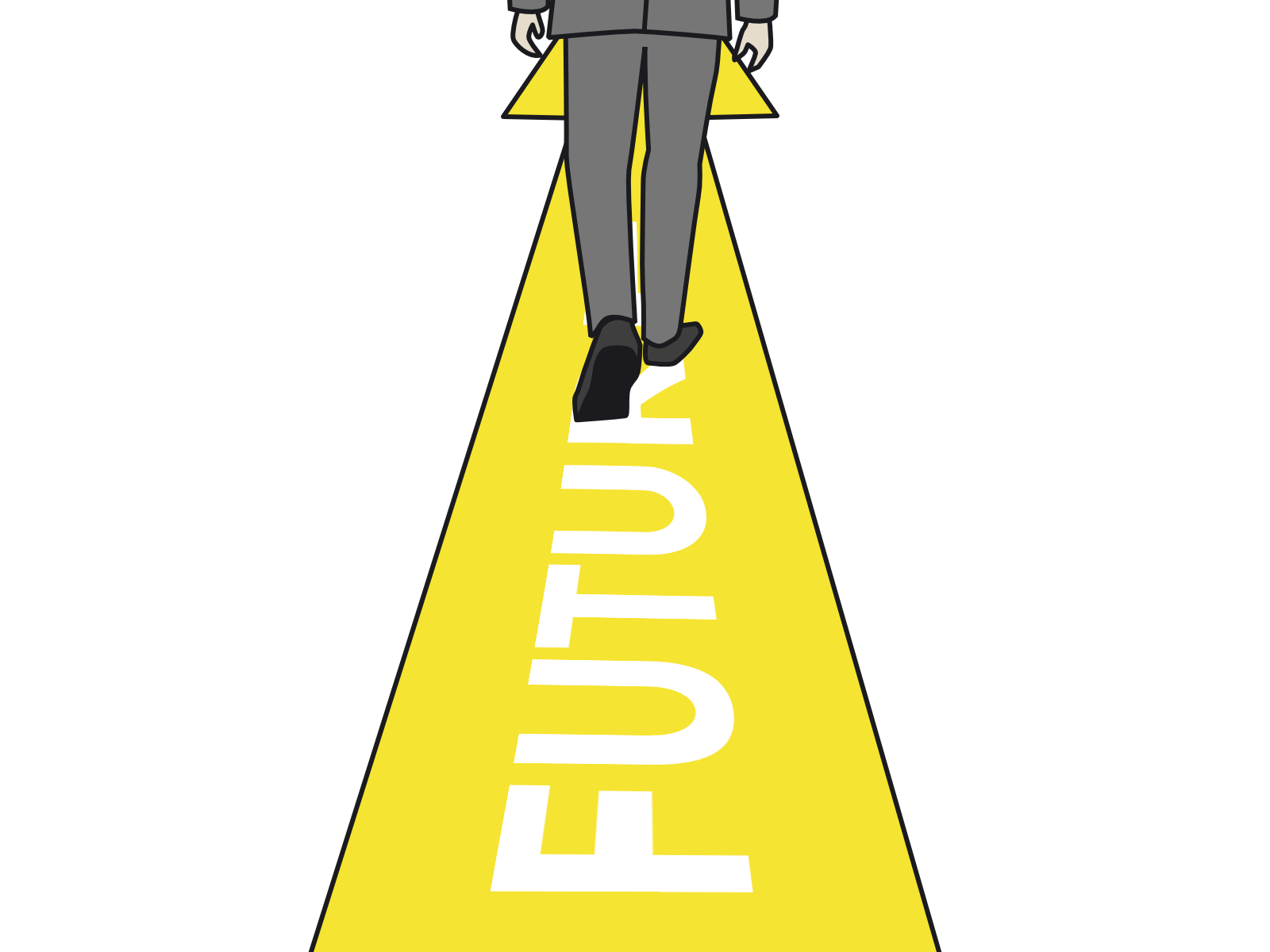
イノベーションは、現在の事業に飛躍をもたらすものです。したがって、既存の組織内でのイノベーションには、おのずと限界があるとドラッカーは考えました。このため、イノベーションを行うための組織は、従来からの活動から独立させなければならないと提言しています。
「新しいものを創造する取り組みと、既存のものの面倒を見ることを同時に行うことはできない」
ドラッカーは、従来の活動とイノベーション活動には全く違ったマネジメントが必要であることを明らかにしました。どちらも重要な活動には違いありませんが、まったく別種の活動であるために、同じ組織内で行おうとすると失敗しやすいということです。イノベーションへの取り組みは、独立した組織によって行う必要があるのです。
製造業の一般的な組織構造では、開発、製造、営業といったように、顧客への価値提供のプロセスの順番に部門がならべられています。ドラッカーはこのような組織は、従来の事業の延長線上の取り組みとなってしまうため、イノベーションにはふさわしくないと考えました。イノベーション活動は、従来の事業からの飛躍が求められているわけですから、それにふさわしい組織構造が必要です。
では、どのような組織がよいのでしょうか。ドラッカーはプロジェクト・チームがイノベーションにふさわしい組織であると考えていました。新しいことにチャレンジしようとする場合には、ただちにプロジェクトを立ち上げ、プロジェクト・リーダーを任命しなければなりません。
プロジェクト・リーダーはどの部門から選んでもよく、特別に専門的な知識も必要ないとしています。しかし、あらゆる部門の協力を仰ぐことができ、また、必要な専門能力を随時利用できるような体制をつくらなければならないと述べています。
ドラッカーは、イノベーションのための組織について、こう述べています。
「既存の事業においては、今いる場所から行こうとする場所へと仕事を組織する。これに対して、イノベーションにおいては、行こうとする場所から、今やらなければならないことへとさかのぼって仕事を組織する。」
つまり、イノベーションのためには、具体的なゴールを設定する必要があるということです。漠然とした意図の下にイノベーションを行うことはできません。あげるべき成果を特定し、具体的な仕事として設定しなければ、イノベーションを起こすことはできないのです。
プロジェクトとは仕事論の基本通りに実行されるべきものなのです。ですから、プロジェクト・リーダーに求められるのは、技術的な専門知識ではなく、マネジメントの能力なのです。
イノベーションの組織は、既存の事業を行う組織の外に、独立してつくらなければなりません。また、イノベーションの組織には、既存の組織からの反発が起きることもあります。
このため、イノベーションを実行するうえでは、変化を当たり前のものと考える組織風土をつくることが大切です。イノベーションのためのプロジェクト・チームの設置が、当たり前のこととして受け止められるような風土をつくることが、継続的なイノベーションのために不可欠なのです。
次回 その31「イノベーションのための七つの機会」
著者紹介
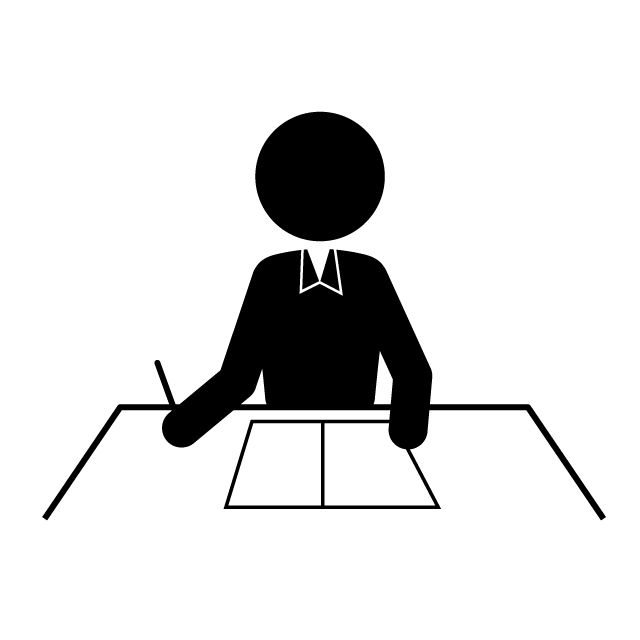 浅沼 宏和
浅沼 宏和
早稲田大学政治経済学部卒、中央大学大学院法学研究科卒、名古屋学院大学 論文博士
「社会制度変容の力学 -内部統制制度・リスクマネジメント・コーポレートガバナンス一体化の論理」
講座に関するご質問、その他通信教育に関するお問合せは、下記担当者までお願いいたします
2025年総合通信教育ガイドについて
ご請求は下記より受け付けております
「一人では変えられないことも、つながれば変わる。」


 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる